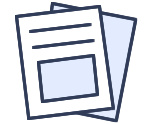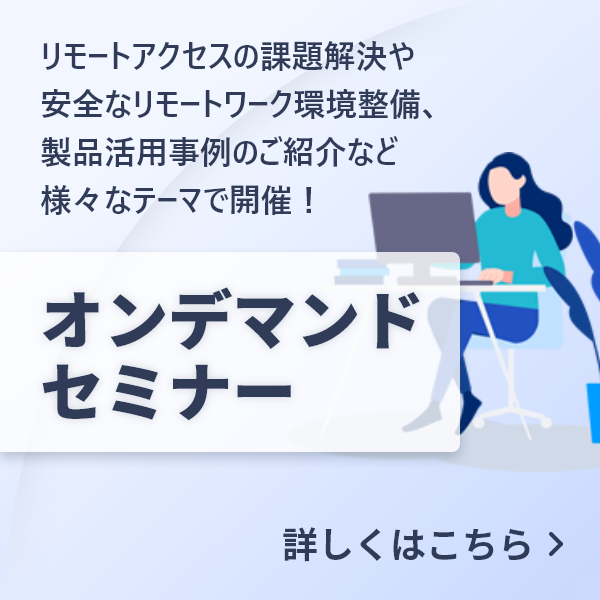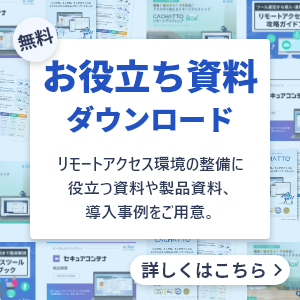BYODの費用負担は誰がする?企業と従業員の適切な負担区分と運用ルール
2025.10.23投稿、2025.10.23更新
BYOD(私物端末の業務利用)を導入する際、最も重要な課題の一つが「費用負担をどうするか」です。通信費や端末代、アプリ費用などを企業が負担すべきか、従業員が負担すべきか、判断に迷う企業も多いでしょう。適切な費用負担ルールを設けないと、労務トラブルや従業員の不満につながるリスクもあります。
本記事では、BYODの費用負担パターンから具体的なコスト比較、企業規模別の実態、よくあるトラブルと対策まで、企業が知っておくべきポイントを詳しく解説します。
BYODの基本情報については、次の記事も参考にしてください。
関連記事

BYODとは?活用のメリット・デメリット、導入や運用するポイントを解説
BYODの費用負担パターンと適切な判断基準
BYODの費用負担には大きく分けて2つのパターンがあります。どちらのパターンを選択するかは、企業の方針や業務形態、従業員の働き方によって決まります。
2つの費用負担パターン(従業員負担・按分負担)
-
従業員負担
通信費や端末の維持費用を従業員が負担する方式です。ただし、業務必須アプリの費用は企業負担とするのが一般的で、企業によっては月額3,000円〜10,000円程度の定額手当を支給することで通信費負担の軽減を図るケースも見られます。
適用ケース
・中小企業で管理リソースが限定的な場合
・端末の個人利用比率が高い職種
・シンプルな制度設計を重視する企業
-
按分負担
業務利用分と個人利用分を合理的に区分し、費用を分担する方式です。最も公平性が高い理論的な方法ですが、按分比率の算定や精算手続きが複雑になるため、現実的には導入のハードルが高い方法です。
適用ケース
・大企業で詳細な費用管理が可能な場合
・業務利用度が職種により大きく異なる企業
・従業員から公平性を強く求められる場合
業務利用度による負担区分の考え方
按分負担を実際に運用する場合、最も重要な判断基準となるのが「業務利用度」です。業務での使用頻度や内容を適切に評価し、以下の要素を総合的に判断して負担割合を決定します。
時間による区分
勤務時間を基準に業務利用度を判断する方法です。平日の勤務時間内(9時~18時など)の利用を企業負担、それ以外の時間の利用を従業員負担とする考え方で、タイムスタンプによる自動計算が可能です。
利用内容による区分
通話先やアクセス先の内容を基準に業務利用度を判断する方法です。取引先や社内への通話、業務システムへのアクセスなどは企業負担とし、個人的な通話やプライベートサイトの閲覧は従業員負担とします。
データ使用量による区分
月間のデータ通信量を基準に業務利用度を判断する方法です。業務で必要な基本的なデータ使用量(メール、Web会議、クラウドアクセスなど)を算定し、それを超過した分を個人利用として従業員負担とする考え方です。
按分負担の算定方法と企業規模別の実態
按分負担は理論的には最も公平な費用分担方法ですが、実際の運用では様々な課題があります。ここでは按分負担の具体的な算定方法と実装上の課題、および企業規模別の費用負担の実態について解説します。
按分比率の算定方法と実装上の課題
按分負担を実際に運用する場合、具体的な計算方法の設計が必要になります。一般的な計算式は以下の通りです。
基本的な計算式
- 時間による区分
業務利用時間 ÷ 総利用時間 × 月額通信費
- 利用内容による区分
業務関連通話時間 ÷ 総通話時間 × 月額通話料
- データ使用量による区分
基本料金 × 按分比率 + 業務による超過料金
しかし、これらの計算方法には実装上の課題があります。業務利用と私的利用の完全な分離が技術的に困難であり、勤務時間内でも個人的な通話がある一方、勤務時間外でも緊急業務対応があるため、正確な区分は現実的ではありません。
また、按分計算のために従業員の利用履歴を詳細に取得することはプライバシーの観点から問題となり、個人情報保護法上の配慮も必要です。さらに、毎月の利用データ収集・分析・精算処理には相当な管理コストがかかり、従業員数が多い企業では按分による節約効果を上回る場合もあります。
これらの理由から按分負担を採用する企業は限定的であり、多くの企業では従業員負担を基本としつつ定額手当で補助する方式を選択しているのが現状です。
企業規模別の費用負担実態
企業規模により費用負担の実態は異なります。大企業では企業負担または月額5,000円から10,000円程度のテレワーク手当による定額支給が一般的です。IT部門の管理体制が整った大企業では、管理の効率性を重視し、従業員の負担を最小限に抑える手厚い支援を選択する傾向があります。
中小企業では、管理リソースの制約から従業員負担を基本とするか、月額3,000円から5,000円程度の簡易的な定額補助に留める企業が多い状況です。複雑な按分計算を避けながら、業務専用アプリの利用料や基本的なセキュリティ対策費用のみを企業負担とする限定的な支援を選択する企業も見られます。
社給端末とBYODの総コスト比較
これらの費用負担方式を踏まえて、BYODと社給端末のどちらを選択すべきかを判断するには、総コストでの比較が重要です。
初期導入費用と運用費用
| 初期導入費用(1台あたり) |
|
社給端末 |
BYOD |
| 端末代 |
50,000円~150,000円 |
0円
(従業員所有) |
| 初期設定費用 |
5,000円~10,000円 |
0円
(従業員による設定) |
| セキュリティ対策費用 |
3,000円~8,000円 |
2,000円~5,000円
(業務領域のみ) |
| MDM導入費用 |
2,000円~5,000円 |
2,000円~5,000円 |
| 初期費用合計 |
60,000円~173,000円 |
4,000円~10,000円 |
| 年間運用費用(1台あたり) |
|
社給端末 |
BYOD |
| 通信費 |
60,000円~120,000円 |
24,000円~60,000円
(按分負担) |
| MDM利用料 |
12,000円~24,000円 |
12,000円~24,000円 |
| 故障・修理費用 |
5,000円~15,000円 |
0円
(従業員負担) |
| 業務用アプリ費用 |
6,000円~12,000円 |
6,000円~12,000円 |
| 年間費用合計 |
83,000円~171,000円 |
47,000円~106,000円 |
※社給端末は買い切り購入の場合を想定
この比較表から分かるように、BYODは初期導入費用で大幅なコスト削減が可能です。特に端末代が不要となることで、初期費用は社給端末の約10分の1以下に抑えられます。初期設定費用やセキュリティ対策費用についても、BYODでは既存の私物端末を活用するため、業務領域のみの設定で済み、社給端末のような全面的な設定作業が不要となることからコストが抑えられます。
年間運用費用についても、通信費の按分負担や故障・修理費用の従業員負担により、社給端末と比べて約40%程度のコスト削減効果が期待できます。
見落としがちな隠れたコスト
一般的なコスト比較では表面化しにくいものの、実際の運用では想定外の費用が発生することがあります。
社給端末では、端末の紛失・盗難時の再調達費用、機種変更時のデータ移行費用、不要端末の処分費用、保険料などが追加で発生する場合があります。一方、BYODでは様々な機種への対応コストや費用精算の管理コスト、セキュリティ管理の複雑化により、想定以上に運用費用が膨らむケースもあります。
これらの隠れたコストも考慮した上で、自社の状況に応じた詳細な試算を行うことが重要です。
費用負担でよくあるトラブルと対策
コスト面でのメリットがあるBYODですが、実際の運用では費用負担に関する様々なトラブルが発生することがあります。ここでは代表的なトラブル事例とその対策について解説します。
従業員とのトラブルと対策
-
按分比率に関する不満
企業が設定した標準按分比率(例:営業職70%、事務職40%など)と従業員の実際の業務利用度に大きな差がある場合、不公平感からトラブルに発展することがあります。特に、業務で頻繁に外出する営業職や、在宅勤務の多い職種では、標準比率では実態を反映できずに従業員の負担が過大になるケースが見られます。また、同じ職種でも個人の働き方や担当業務により利用度が大きく異なるため、一律の按分比率では公平性を保てないという問題もあります。
【対策】
・利用実態の詳細な調査を実施
・按分比率の見直しと明確な基準の策定
・職種別の標準比率の設定
-
費用精算の遅延
月末や四半期末など申請が集中する時期に経理部門の処理が追いつかず、精算に1~2ヶ月程度かかってしまう問題があります。特に中小企業では経理担当者が限られており、通常業務に加えてBYOD関連の精算処理を行うため、処理能力を超えてしまうケースが多く見られます。また、申請書類の不備や承認フローの複雑さも遅延の要因となり、従業員の立替負担が長期化することで不満につながります。
【対策】
・精算システムの自動化推進
・処理スケジュールの明確化
・緊急時の仮払い制度の導入
-
高額な通信費の発生
海外出張時のローミング料金や想定を超える大容量データ通信により、月額数万円の予期しない高額請求が発生することがあります。特に動画会議の頻用や大容量ファイルのダウンロード、クラウドストレージの同期処理などにより、従業員が気づかないうちにデータ使用量が急増するケースが見られます。
【対策】
・海外利用時の事前承認制度
・月額上限額の設定
・代替手段(Wi-Fiレンタル等)の提供
コンプライアンス上のリスクと対策
-
労働基準法違反のリスク
従業員に過度な費用負担を求めることで、労働基準法第89条(就業規則記載事項)に抵触する可能性があります。特に、業務に必要な通信費を全額従業員負担とした場合や、手当額が実際の負担額を大幅に下回る場合は、実質的な賃金の減額とみなされるリスクがあります。また、費用負担に関するルールが就業規則に明記されていない場合や、従業員の同意を得ずに一方的に負担を求めた場合も問題となります。
【対策】
・就業規則への明確な記載
・従業員の事前同意取得
・負担額の合理性確保
-
個人情報保護法上のリスク
按分計算のために従業員の通話履歴やアクセスログ、位置情報などの利用データを取得・分析する際は、個人情報保護法に基づく適切な手続きが必要です。利用目的を明確に示し、従業員からの同意を適切に取得しないまま詳細なデータ収集を行った場合、法令違反となる可能性があります。
【対策】
・利用目的の明示
・必要最小限の情報取得
・適切な管理体制の構築
適切な費用負担ルールでBYOD導入を成功させよう
BYODの費用負担は、企業規模と業務実態に応じた現実的な選択が重要です。大企業では企業負担または定額手当、中小企業では従業員負担または限定的な補助というように、管理リソースとのバランスを考慮した制度設計が求められます。
按分負担は理論的には最も公平ですが、実装の複雑さから採用企業は限定的です。むしろ、明確で管理しやすいルールを策定し、従業員が納得できる透明性を確保することが成功の鍵となります。
BYODの導入でコスト削減を実現しながら、同時にセキュリティリスクを最小限に抑えたい企業には「セキュアブラウザ」の活用がおすすめです。スマートフォンやタブレット、PCから社内システムやクラウドサービスへ安全にアクセスでき、端末にデータを一切残さない仕組みで情報漏洩リスクを極小化します。スクリーンショット禁止やコピー&ペースト禁止などのセキュリティ機能により、私用端末を業務利用する際の不安を解消できるため、メール返信や予定確認、Webシステムの利用など、隙間時間での軽微な業務に最適です。適切な費用負担ルールと合わせて導入することで、BYODのコスト削減効果とセキュリティを両立した環境を構築できます。
CACHATTO Oneに関する資料請求やお問い合わせはこちら。
お気軽にお問い合わせください!
リモートアクセスや製品に関する
お役立ち資料をご用意しています。
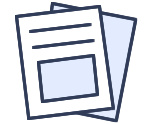 お役立ち資料ダウンロード
お役立ち資料ダウンロード
リモートアクセスや製品に関する
様々なご質問にお答えします。
 メールでお問い合わせ
メールでお問い合わせ