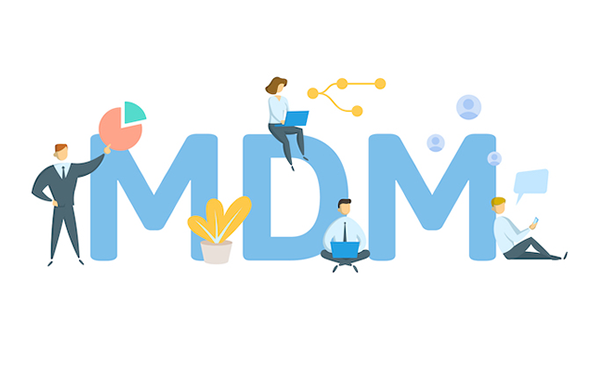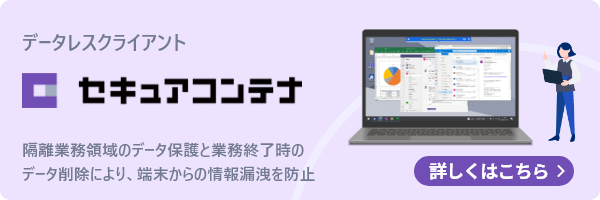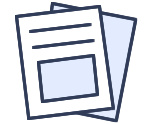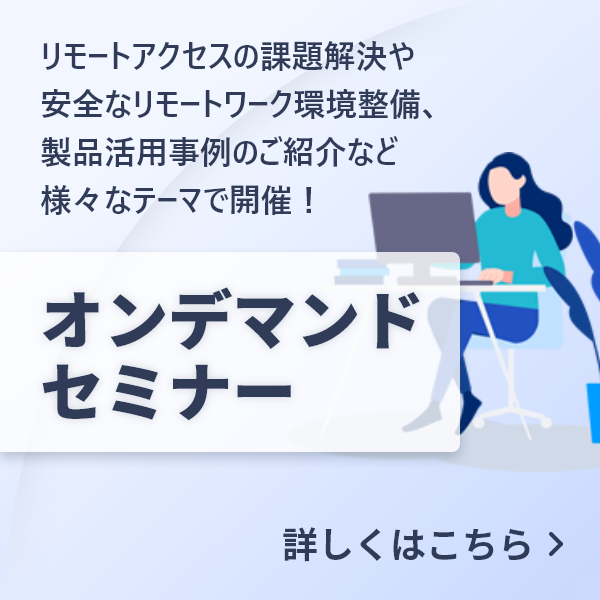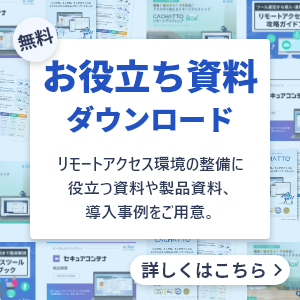シャドーIT対策の実装手順|4段階アプローチで実現するセキュアな業務環境
2025.10.16投稿、2025.10.16更新
近年、テレワークの普及に伴い、企業が把握していないITツールやサービスを従業員が独自に利用する「シャドーIT」が問題となっています。しかし、シャドーITの存在は認識していても、「具体的にどう対策すればよいのか分からない」と感じている担当者もいるのではないでしょうか。
単純にシャドーITを禁止するだけでは、従業員の業務効率が低下し、かえって隠れた利用が増加する可能性があります。重要なのは、セキュリティを確保しながら従業員の利便性も両立する、体系的なアプローチです。
本記事では、シャドーIT対策を「発見」「統制」「代替提供」「継続運用」の4つのフェーズに分けて、具体的な実装手順と成功のポイントを解説します。
シャドーITの基本情報については、次の記事も参考にしてください。
関連記事

シャドーITとは?起こりうるセキュリティリスクや防止策を解説
【発見フェーズ】シャドーITの可視化
シャドーIT対策の第一歩は、組織内でどのような未承認ツールやサービスが利用されているかを正確に把握することです。見えない脅威に対処するためには、まず現状を可視化する必要があります。
ネットワーク監視による自動検出
技術的なアプローチとして、ネットワーク監視ツールを活用した自動検出が効果的です。ファイアウォールログやプロキシサーバーのアクセスログを分析することで、企業ネットワークから外部クラウドサービスへの通信パターンを把握できます。
具体的には、Dropbox、Google Drive、Slack、Zoomなどの主要なクラウドサービスへのアクセス頻度や、データ転送量を監視します。特に大容量ファイルのアップロードや、業務時間外のアクセスパターンは、シャドーIT利用の兆候として注意深く監視すべきポイントです。
また、DNS問い合わせログの分析も有効です。従業員が新しいクラウドサービスにアクセスする際、最初にDNS問い合わせが発生するため、未知のサービスドメインへのアクセスを検出できます。
これらの監視活動をより効率的に実施するためには、CASB(Cloud Access Security Broker)ソリューションの活用も有効です。CASBは、クラウドサービスの利用状況を包括的に可視化し、「可視化」「コンプライアンス」「データセキュリティ」「脅威制御」の4つの観点から統合的な管理を実現します。特に、未知のクラウドサービスへのアクセスを自動検出し、業務要件に応じた代替サービス選定の判断材料として活用できる点で重要です。
これらの監視データを統合的に分析することで、組織内のシャドーIT利用実態の全体像を把握できます。
CASBについては、次の記事も参考にしてください。
関連記事

CASBとは?主な機能や導入するメリット・デメリット、選定時のポイントを解説
従業員調査とリスク評価
技術的な監視だけでは発見できないシャドーITも存在するため、従業員への直接調査も重要な手段です。ただし、アプローチを誤ると従業員の警戒心を招き、かえって隠蔽を促進する可能性があるため、慎重な進め方が必要です。
効果的なアプローチは、「問題追及」ではなく「業務改善」の観点から調査を実施することです。「現在の業務で不便に感じていることは何か」「より効率的に業務を進めるために、どのようなツールを使いたいか」といった建設的な質問を中心に据えることで、従業員からの率直な回答を得やすくなります。
調査で発見されたシャドーITは、リスクレベルに応じて分類します。機密情報を扱う可能性の高いツール、外部との情報共有が発生するサービス、認証機能が弱いアプリケーションなどを高リスクとして優先的に対処します。一方、業務効率化に寄与し、セキュリティリスクが比較的低いツールについては、正式な承認プロセスを経て利用を認めることも検討します。
【統制フェーズ】段階的な制御施策
シャドーITの実態が把握できたら、次は段階的な制御施策を実装します。一度にすべてを制限すると業務に大きな支障をきたすため、計画的なアプローチが重要です。
アクセス制御とエンドポイント管理
まず、ネットワークレベルでのアクセス制御を強化します。ファイアウォールやプロキシサーバーの設定を見直し、高リスクと判定されたクラウドサービスへのアクセスを段階的に制限します。
並行して、エンドポイント管理の強化も進めます。MDM(モバイルデバイス管理)やEMM(エンタープライズモビリティ管理)ソリューションの導入により、企業支給デバイスでのアプリケーションインストールを制御できます。これらのソリューションには、承認されていないアプリケーションの自動検出・削除機能や、事前に承認されたアプリケーションのみインストールを許可する機能があり、効果的な制御が可能です。
個人所有デバイス(BYOD)への対応も重要な要素です。完全に禁止するのではなく、セキュリティ要件を満たした上での利用を認める方針を検討します。具体的には、業務利用時のみVPN接続を必須とする、特定のセキュリティアプリケーションのインストールを条件とするなど、段階的な制御を実装します。
MDMについては、次の記事も参考にしてください。
関連記事
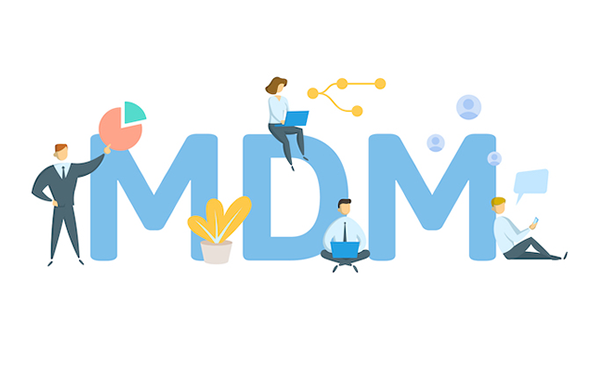
BYODに欠かせないMDMとは?メリット・デメリットもあわせて紹介
段階的実装の進め方
制御施策の実装は、業務への影響を最小限に抑えながら確実にセキュリティを向上させるため、段階的なアプローチで進めることが重要です。
一度にすべてのシャドーITを制限すると業務に大きな支障をきたすため、警告・啓発から始めて、代替手段の提供を経て、最終的に完全制御に移行する流れが効果的です。各段階では、従業員の業務ニーズを十分に把握し、適切な代替ソリューションを提供することで、セキュリティ向上と業務効率の両立を図ります。
実装のタイミングや期間は、組織の規模、業務特性、既存システムとの統合度合い、従業員のITリテラシーレベルなどを総合的に考慮して決定する必要があります。
【代替提供フェーズ】承認済みソリューションの整備
シャドーITを制限するだけでは根本的な解決にはなりません。従業員のニーズを満たす安全で使いやすい代替ソリューションの提供により、セキュリティ向上と業務効率の両立を実現できます。
シャドーIT利用要因の分析と代替ソリューション要件の整理
シャドーIT利用の主要な要因は、既存システムの機能不足や制約にあります。社内ファイルサーバーの容量制限、VPN接続の複雑さ、リモートワークへの対応不足などから、従業員が利便性を求めて外部サービスを選択している実態があります。
これらの要因分析から、従業員の業務ニーズに基づく代替ソリューションの要件を整理します。一般的なクラウドサービスでは、十分なストレージ容量、直感的な操作性、モバイル対応、既存システムとの連携性が求められます。特にリモートアクセス領域では、従来のVPN接続の課題を解決し、セキュリティと利便性を両立する技術的解決策が必要です。
この分析結果を踏まえ、業務ニーズを満たしながら企業のセキュリティポリシーを遵守できるソリューション選定に向けて、具体的な選定基準の策定と技術ソリューションの評価を進めていきます。
企業向けクラウドサービスの選定基準
代替ソリューションの選定では、セキュリティ要件と業務効率の両立が重要です。まず、データの保存場所や暗号化方式、アクセス制御機能、監査ログの取得可能性などのセキュリティ要件を明確に定義します。特に、GDPRや個人情報保護法などの法規制への対応状況も重要な選定基準です。
次に、既存のITインフラとの統合性を評価します。Active DirectoryやAzure ADとの連携機能、既存のメールシステムやグループウェアとの親和性、APIによる他システムとの連携可能性などを検証します。
ユーザビリティの観点では、従業員が現在使用している未承認ツールと同等以上の使いやすさを確保することが重要です。インターフェースの直感性、モバイル対応状況、オフライン機能の有無などを総合的に評価し、従業員の業務効率を損なわないソリューションを選定します。
データレスクライアントによる安全なリモートアクセス
シャドーIT対策において特に有効なのが、データレスクライアントソリューションの活用です。VPN接続の複雑さやリモートワークでの利便性不足といったアクセス環境の課題を解決し、従業員が個人端末で業務を継続したいというニーズに対して安全で使いやすい環境を提供することで、未承認クラウドサービスの利用動機を軽減できます。
さらに、データレスクライアントはセキュリティ面でも大きなメリットがあります。従来のVPN接続では、クライアント端末に業務データがダウンロードされ、端末の紛失や盗難時に情報漏洩リスクが発生します。一方、データレスクライアントでは、端末上に隔離されたセキュアな業務領域を生成し、その中でのみ業務を行うため、端末の通常領域にデータが残りません。業務終了時には業務領域が自動削除されるため、データ漏洩リスクを大幅に軽減できます。
この方式により、従業員は使い慣れた自分のデバイスで業務を継続でき、MDMによるリモートワイプ機能に頼らずとも高いセキュリティレベルを維持できます。さらに、利用状況の詳細なログを取得できるため、コンプライアンス要件への対応や、セキュリティインシデント発生時の原因調査にも役立ちます。
データレスクライアントについては、次の記事も参考にしてください。
関連記事

データレスクライアントとは?仕組みやVDIとの違い、メリット・デメリットを解説
【継続運用フェーズ】組織体制の構築と定着化
シャドーIT対策は一度実装すれば完了というものではありません。新しいクラウドサービスは次々と登場し、業務要件も常に変化するため、継続的な運用体制の構築が不可欠です。
セキュリティガバナンス体制の構築
CISO(最高情報セキュリティ責任者)を中心とした横断的なセキュリティ委員会を設置し、定期的なリスクアセスメントを実施する体制を構築します。
委員会では、新たに発見されたシャドーITの評価、既存対策の効果検証、新しい脅威への対応策検討などを実施します。また、各部門からセキュリティ担当者を選出し、現場レベルでのセキュリティ意識向上と早期発見体制の構築を推進します。
新しいクラウドサービスや業務ツールの導入を検討する際の評価プロセスについても標準化が必要です。セキュリティ要件、コンプライアンス要件、技術的要件、コスト要件などの評価項目を明確に定義し、客観的な判断基準に基づいた導入可否の決定を行います。
継続的運用とインシデント対応
組織的なガバナンス体制を構築した後は、継続的な監視と運用が重要になります。ネットワークトラフィック分析、エンドポイント監視、クラウドサービス利用状況の定期レビューなどの監視活動を継続的に実施し、自動化ツールを活用して異常なアクセスパターンを検出することで、新たなシャドーIT利用の兆候を早期に発見する体制を整備します。
万が一シャドーIT関連のインシデントが発生した場合に備えて、対応プロセスの標準化も欠かせません。発見から初動対応、影響範囲の調査、復旧作業、再発防止策の検討まで、一連の流れを明文化し、迅速かつ適切な対応を可能にします。
技術的な対策と並行して、従業員教育の継続的な実施も重要な要素です。新人研修でのセキュリティ教育に加え、定期的な啓発セミナーや最新の脅威情報の共有を行います。特に、シャドーITのリスクを具体的な事例とともに説明し、従業員一人ひとりのセキュリティ意識向上を図ります。
さらに効果的な取り組みとして、従業員からの相談窓口を設置し、新しいツールの利用を検討している際に気軽に相談できる環境を整備します。相談しやすい雰囲気作りにより、隠れたシャドーIT利用を防止し、適切な代替ソリューションの提案につなげることができます。
4段階アプローチで実現するシャドーIT対策
シャドーIT対策は、単発の施策では効果的な解決は困難です。本記事で紹介した4段階のアプローチ「発見フェーズでの可視化」「統制フェーズでの段階的制御」「代替提供フェーズでの安全なソリューション整備」「継続運用フェーズでの組織的対策」を体系的に実装することで、セキュリティと利便性を両立した業務環境を実現できます。
特に重要なのは、シャドーITを単に禁止するのではなく、従業員のニーズを満たす安全な代替手段を提供することです。データレスクライアントのようなソリューションを活用すれば、個人端末からでも企業データを安全に扱える環境を構築でき、シャドーIT発生の根本的な動機を解決できます。
例えば、データレスクライアントである「セキュアコンテナ」では、隔離されたセキュアな業務領域を生成し、その中でのみ業務を行うことができるため、端末内に業務データを残すことなく、高度なセキュリティを実現します。業務終了時にはその領域を削除するため、MDMの導入やリモートワイプを使用せずとも、万が一端末の紛失や盗難が発生した場合でも、重要なデータを失う心配がありません。さらに、スマートフォンやタブレットからのセキュアブラウザによる作業にも対応しているため、多様な働き方にも柔軟に対応できます。
CACHATTO Oneに関する資料請求やお問い合わせはこちら。
お気軽にお問い合わせください!
リモートアクセスや製品に関する
お役立ち資料をご用意しています。
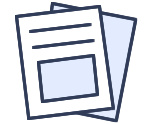 お役立ち資料ダウンロード
お役立ち資料ダウンロード
リモートアクセスや製品に関する
様々なご質問にお答えします。
 メールでお問い合わせ
メールでお問い合わせ