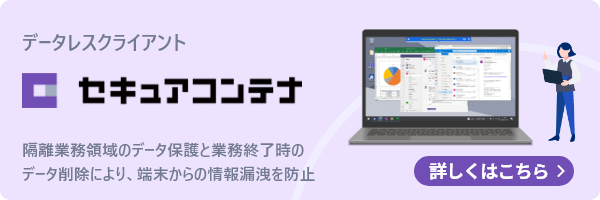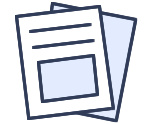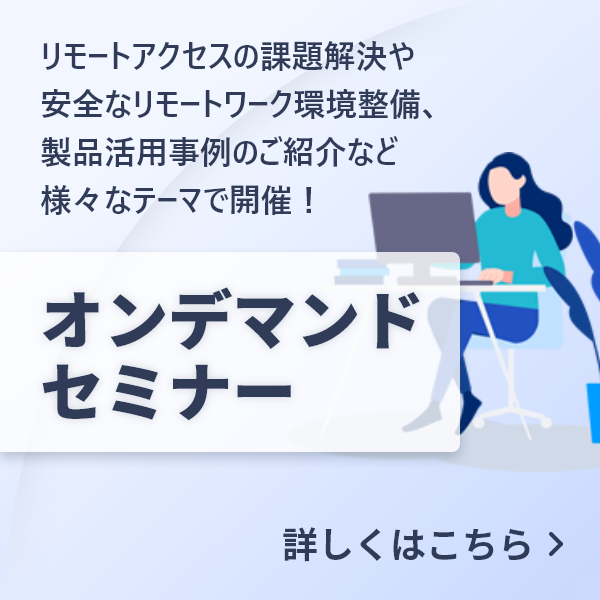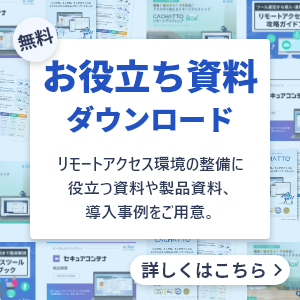知っておくべきデータ持ち出しリスク - 企業の情報資産を守るための効果的な対策
2025.10.14投稿、2025.10.14更新
近年、企業における情報漏洩事件が相次ぎ、その多くは内部からのデータ持ち出しが原因となっています。クラウドサービスの普及やリモートワークの一般化により、企業データの持ち出しリスクは年々高まっています。しかし多くの企業、特に中小企業ではセキュリティ対策が十分に整備されておらず、データ持ち出しのリスクに無防備な状態に置かれています。
本記事では、データ持ち出しが企業にもたらすリスク、持ち出しが行われる状況、効果的な対策方法、そして万が一の際の事後対応まで解説します。
データ持ち出しの実態と企業が直面する深刻なリスク
企業情報の持ち出しは単なるセキュリティ問題ではなく、経営そのものを脅かす深刻なリスクとなっています。内部不正による情報漏洩の動向、企業価値への影響、法的責任について詳しく見ていきましょう。
内部不正による情報漏洩の現状と増加傾向
情報処理推進機構(IPA)が発表した「情報セキュリティ10大脅威 2024」によると、「内部不正による情報漏えい等の被害」は組織向け脅威の第3位に位置付けられており、2016年の初選出以来9年連続でランクインしている深刻な問題です。これは、外部からの攻撃である「ランサムウェアによる被害」や「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃」と並ぶ主要な脅威となっています。
特に注目すべきは、パンデミック以降のリモートワークの普及により、社内データを社外に持ち出す機会が劇的に増加したことです。テレワーク環境下では、社員のPCやスマートフォンからの情報漏洩リスクがさらに高まり、従来の対策では十分に対応できない状況が生まれています。
内部不正は外部からの攻撃と比較して検知が難しく、発覚までに長期間を要することが多いという特徴があります。被害が表面化したときには、すでに甚大な損害が生じていることも少なくありません。
企業価値の低下 - 競争力の喪失と顧客信頼の損失
企業の機密情報が外部に漏洩した場合、その影響は計り知れません。技術情報や製品開発データが競合他社に渡れば、長年かけて構築した競争優位性が一瞬にして失われることになります。特に知的財産が企業価値の中核を担う業種では、情報漏洩は企業存続そのものを脅かす重大な危機となり得ます。
また、顧客情報や取引先情報の漏洩は、企業の社会的信頼を大きく損ないます。情報漏洩事件が発生すると、消費者や取引先からの信頼回復には相当な時間を要し、その間の売上減少や取引縮小、風評被害対応など目に見えない損失も含め、企業経営に深刻な打撃を与えることになります。
法的責任と罰則
企業が保有するデータの持ち出しによる情報漏洩は、様々な法的責任を発生させます。個人情報が含まれる場合は、個人情報保護法違反となり、法人に対して高額な罰金が科される可能性があります。また、営業秘密の漏洩は不正競争防止法に抵触し、組織と個人の両方に厳しい罰則が設けられています。
さらに、漏洩した情報の種類や範囲によっては、民事上の損害賠償責任も発生します。企業の安全管理措置の不備が認められた場合、被害規模によっては多額の賠償金支払いを命じられることもあり、経営に大きな影響を与えかねません。
なぜ起こる?社員によるデータ持ち出しの典型的パターン
データ持ち出しが発生する背景には様々な理由があります。悪意のある行為だけでなく、善意や無自覚による情報漏洩も少なくありません。代表的なパターンを理解することで、効果的な対策の第一歩となります。
悪意ある持ち出し
データ持ち出しの中で最も深刻なのは、明確な意図を持って行われる悪意ある持ち出しです。典型的なケースとしては、退職予定者が転職先や独立後に活用する目的で顧客リストや設計図などの機密情報をコピーするというものがあります。また、金銭目的で外部の第三者に情報を売却するケースも存在します。
この種の持ち出しの危険性は、行為者が発覚を避けるために様々な手段を講じる点にあります。USBメモリの使用が制限されている環境では、個人のクラウドストレージを利用したり、メールで自分自身に送信したりといった手段が用いられることもあります。また、スクリーンショットを撮影してスマートフォンに保存するなど、監視の目を逃れるための工夫がなされることも少なくありません。
善意による違反
一方で、必ずしも悪意なく行われるデータ持ち出しも数多く存在します。典型的なのは、「自宅で作業を続けたい」「移動中に資料を確認したい」といった業務効率化を目的としたケースです。特にリモートワークやフレックスタイム制の導入により、こうした「善意の違反」は増加傾向にあります。
問題は、こうした社員が必ずしも適切なセキュリティ対策を講じているとは限らない点です。セキュリティが確保されていない自宅のPC、公共Wi-Fiに接続したデバイス、家族と共有するタブレットなどで機密情報を扱うことで、意図せず情報漏洩のリスクを高めてしまいます。
無自覚な漏洩
最も防ぎにくいのが、セキュリティ意識の欠如による無自覚な漏洩です。「この程度の情報なら大丈夫だろう」という安易な判断で、業務関連の内容をSNSで発信したり、不特定多数が参加するオンライン会議で機密情報を画面共有したりするケースが増えています。
また、フィッシングメールへの誤った対応や、マルウェア感染による情報流出など、社員のセキュリティリテラシー不足に起因する漏洩も後を絶ちません。こうした無自覚な漏洩は、本人が問題を認識していないため発見が難しく、対策が後手に回りがちです。
データ持ち出しの経路別・実効性ある対策と監視方法
データ持ち出しの経路は多様化しており、それぞれに適した対策が必要です。物理媒体からネットワーク経由、そして人的要因まで、様々な角度からの防御策を検討します。
物理媒体とモバイル機器への対策
最も基本的な対策は、USBメモリや外付けハードディスクなどの外部記録媒体の使用制限です。多くの企業では、特定のポートやデバイスへのアクセスを制限するデバイス制御ソフトウェアを導入しています。ただし、業務上必要なケースも存在するため、一律禁止ではなく、使用申請制や書き込み専用デバイスの導入など、業務効率を損なわない形での運用が求められます。
また、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器についても、カメラ機能の制限やMDM(モバイルデバイス管理)ツールの導入により、社内情報の不正な持ち出しリスクを低減することができます。特にBYOD(個人所有デバイスの業務利用)を許可している企業では、業務用と個人用の領域を明確に分離することが重要です。
モバイル機器のBYODやMDMについては、次の記事も参考にしてください。
関連記事

スマホでのBYOD実践~企業が知るべき責任と効果的な運用方法
関連記事

MDMを自社に合わせて選ぶには?MDMの機能や導入の流れもわかりやすく解説
ネットワーク経由の漏洩防止
クラウドストレージやWebメールを利用した情報持ち出しを防ぐためには、ネットワークレベルでの対策が不可欠です。多くの企業ではWebフィルタリングを導入し、未承認のクラウドサービスへのアクセスをブロックしています。ただし、完全な遮断は業務効率を著しく低下させるリスクがあるため、適切なサービスを選定し、企業管理下で利用できる環境を整備することが望ましいでしょう。
また、DLP(データ漏洩防止)ソリューションの導入により、メールやWeb通信を監視し、機密情報の社外送信を検知・ブロックすることも効果的です。特に個人情報や機密性の高いキーワードを含むデータの送信をリアルタイムで検知することで、意図的・非意図的を問わない情報漏洩を防止できます。
DLPについては、次の記事も参考にしてください。
関連記事

DLPとは?内部不正やヒューマンエラーによる情報漏洩を防ぐポイントを解説
退職者発生時のデータ消去と権限管理
情報漏洩リスクが最も高まるのは、社員の退職時です。退職が決まった時点で、即座にアクセス権限を適切に制限することが重要です。具体的には、機密情報へのアクセス権を段階的に縮小し、最終出社日にはすべての権限を削除する運用が推奨されます。
また、社員が使用していた端末のデータ消去と初期化も徹底する必要があります。単なるファイル削除ではなく、データ復元ができないレベルでの消去が必要です。さらに、クラウドサービスやSaaSツールのアカウント管理も忘れてはなりません。退職者のアカウントを速やかに無効化し、権限の見直しを行うことで、退職後のアクセスリスクを排除します。
データレスクライアントによる根本的解決
データ持ち出し問題に対する根本的な解決策として注目されているのが、データレスクライアントです。この技術は「端末内にデータを残さない」という原則に基づいており、情報漏洩リスクを構造的に解消します。具体的には、端末上に暗号化された作業領域を一時的に生成し、業務終了時にはこの領域ごと完全に消去します。これにより、USBメモリの制限や監視システムといった従来の対処療法的アプローチとは異なり、データ持ち出しの可能性自体を排除できます。従来のVDIより負担が軽く導入しやすく、リモートワーク環境にも適応できるため、企業のセキュリティ対策の新たな標準として急速に普及しています。
データレスクライアントについては、次の記事も参考にしてください。
関連記事

データレスクライアントとは?仕組みやVDIとの違い、メリット・デメリットを解説
データ持ち出し発覚後の適切な対応ステップ
情報漏洩が発覚した際の対応は、その後の企業の命運を左右します。初動対応から法的措置、再発防止策まで、迅速かつ適切な行動計画を解説します。
初動対応
データ持ち出しが発覚した場合、まず優先すべきは被害拡大の防止です。該当する情報システムへのアクセス制限、漏洩が疑われる従業員のアカウント停止などの緊急措置を講じた上で、情報収集を行います。
調査では、アクセスログ解析、端末のフォレンジック調査、関係者へのヒアリングなどを通じて、いつ、誰が、どのような情報を、どのような方法で持ち出したのかを特定します。この際、証拠保全の観点から、調査プロセスの記録や証拠の適切な保存も重要です。
法的措置と対外対応
データ持ち出しの全容が明らかになったら、次に考えるべきは法的措置と対外的な信頼回復です。法的対応としては、行為者に対する懲戒処分や損害賠償請求、状況に応じた刑事告発などが検討されます。これらは単なる制裁ではなく、組織の姿勢を示す重要な意思表示でもあります。
同時に、顧客や取引先など影響を受けるステークホルダーへの適切な情報開示も不可欠です。個人情報保護委員会など関係機関への報告義務がある場合は速やかに対応し、透明性のある説明と謝罪、そして具体的な再発防止策の提示によって信頼回復に努めます。特に、事実隠蔽や報告遅延は二次的な信頼損失を招くため、迅速かつ誠実な対応が求められます。
再発防止策の構築
事案の全容が明らかになったら、類似事案の再発を防ぐための対策を検討・実施します。技術的対策として、アクセス権限の見直し、監視体制の強化、DLPツールの導入などが考えられます。
同時に組織的対策として、セキュリティポリシーの見直し、従業員教育の強化、内部通報制度の整備なども重要です。特に、今回の事案発生の背景・原因を踏まえた実効性のある対策を講じることが、真の再発防止につながります。
効果的なデータ持ち出し対策で企業資産を守る
データ持ち出しは企業にとって見過ごせないリスクであり、技術的対策と組織的対策の両面からの取り組みが不可欠です。特に中小企業では限られたリソースの中でも効果的な対策を講じる必要があります。本記事で紹介した対策手法、特にデータレスクライアントのような先進的アプローチを検討し、自社の状況に合わせた最適な防御策を構築しましょう。情報漏洩は「起きたら対応する」ものではなく「起こさないようにする」ものです。今日から始められる対策を着実に実行し、大切な企業資産を守っていきましょう。
例えば、データレスクライアントである「セキュアコンテナ」なら、隔離されたセキュアな業務領域を生成し、その中でのみ業務を行うことができるため、端末内に業務データを残すことなく、高度なセキュリティを実現します。業務終了時にはその領域を削除するため、MDMの導入やリモートワイプを使用せずとも、万が一端末の紛失や盗難が発生した場合でも、重要なデータを失う心配がありません。さらに、スマートフォンやタブレットからのセキュアブラウザによる作業にも対応しているため、多様な働き方にも柔軟に対応できます。
CACHATTO Oneに関する資料請求やお問い合わせはこちら。
お気軽にお問い合わせください!
リモートアクセスや製品に関する
お役立ち資料をご用意しています。
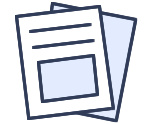 お役立ち資料ダウンロード
お役立ち資料ダウンロード
リモートアクセスや製品に関する
様々なご質問にお答えします。
 メールでお問い合わせ
メールでお問い合わせ