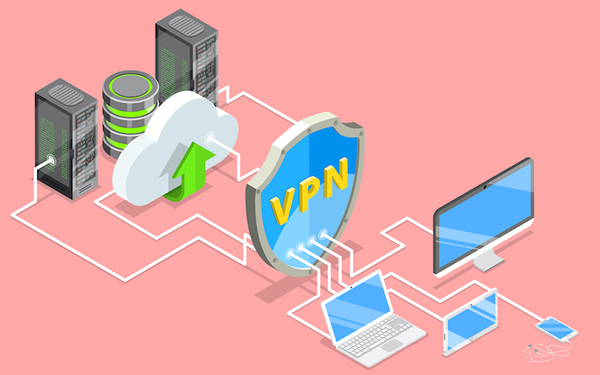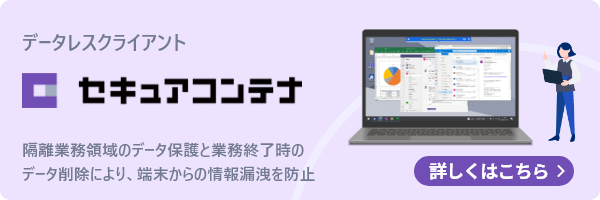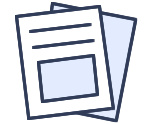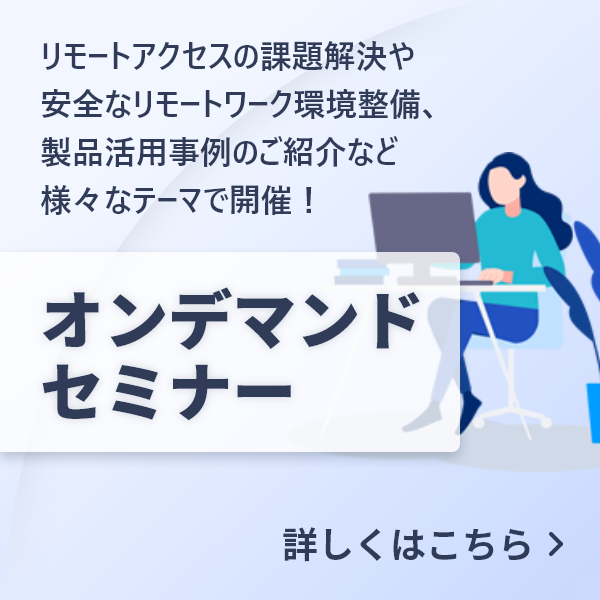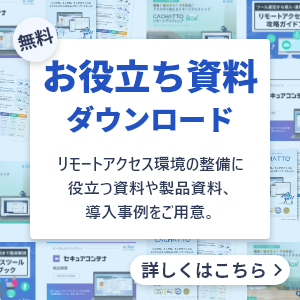VPNは本当に安全か?知っておくべきリスクと対策、次世代セキュリティの選択肢
2025.08.12投稿、2025.08.12更新
企業のリモートアクセスセキュリティの要として長年信頼されてきたVPNですが、サイバー攻撃の高度化に伴い、その安全性に対する疑問が高まっています。多くの組織で根付いている「VPNを導入していれば安全」という認識は、今や根本的な見直しを迫られています。
本記事では、VPNセキュリティの盲点、実際に発生した攻撃事例、そして次世代型セキュリティの選択肢までを解説し、より安全なリモートアクセス環境構築のためのアプローチを提案します。
VPNセキュリティの実態 - 見過ごされてきた脆弱性とリスク
VPNは「Virtual Private Network(仮想プライベートネットワーク)」の略で、インターネット上に仮想的な専用線を構築することで、リモート環境から安全に社内ネットワークへアクセスするための技術です。企業の情報セキュリティ対策として広く普及していますが、その安全性には多くの誤解と盲点が存在します。
VPNについては、次の記事も参考にしてください。
関連記事
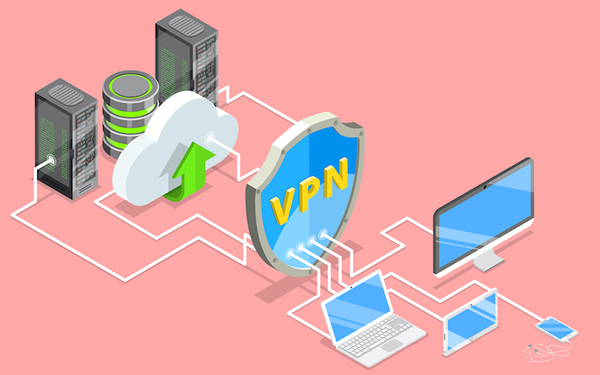
VPNとは?仕組みやプロトコルの種類、接続方式などを解説
VPNが抱える3つの根本的な脆弱性
VPNゲートウェイが単一障害点となるリスク
VPN接続の要となるVPNゲートウェイは、企業の内部ネットワークへの出入口として機能しています。この構造には、VPNゲートウェイが「単一障害点(Single Point of Failure)」となる危険性が潜んでいます。つまり、VPNゲートウェイが攻撃者に侵害された場合、企業のネットワーク全体が危険にさらされる恐れがあります。
特に問題なのは、VPNゲートウェイが外部からアクセス可能なインターネット上に公開されているという点です。これにより、世界中のサイバー攻撃者による標的となりやすく、セキュリティ脆弱性が発見されるとすぐに攻撃対象となります。
認証情報の脆弱性
多くのVPN実装では、ユーザー名とパスワードという比較的シンプルな認証方式を採用しています。この方式の問題点は、認証情報が漏洩した場合、攻撃者が正規ユーザーとして簡単に侵入できることです。
パスワードリスト攻撃やフィッシング攻撃により、VPN認証情報が漏洩するケースは少なくありません。さらに、未だに多要素認証を導入していないVPN環境も多く、認証情報の窃取による不正アクセスのリスクが高い状態が続いています。
内部ネットワーク全体へのアクセスを許す過剰な信頼構造
VPNの最も根本的な問題は、「境界型セキュリティモデル」に基づいているという点です。つまり、VPN認証さえ突破すれば、内部ネットワーク全体にアクセスできるという「過剰な信頼」の上に成り立っています。
このモデルでは、一度VPN接続が確立されると、ユーザーは広範囲のネットワークリソースにアクセスできるようになります。これは「城壁と堀」型のセキュリティとも呼ばれ、いったん城壁(VPN)を突破されると、内部は比較的自由に動き回れる状態になります。この構造は、内部侵入後の横方向移動(ラテラルムーブメント)を容易にし、被害を拡大させる要因となっています。
VPN製品自体の深刻な脆弱性の実態
VPN製品のパッチ管理における現実的課題
VPNアプライアンスやソフトウェアでは、深刻な脆弱性が定期的に発見されています。この状況において大きな問題となっているのが、脆弱性の発見から実際の保護までの「タイムラグ」です。このプロセスには以下のような複数の段階があります。
- 脆弱性の発見から公表までの期間
- ベンダーによるパッチ開発・リリースまでの期間
- 企業がパッチの存在を認識するまでの期間
- 企業がパッチを検証し適用するまでの期間
特に3と4の段階において、多くの企業では深刻な遅延が発生しています。セキュリティ機関やベンダーから緊急の対応が推奨されているにもかかわらず、パッチ公開から数ヶ月経過しても未対応の企業が少なくありません。
このような状況において、攻撃者は脆弱性情報が公開されると迅速に攻撃コードを開発し、パッチ未適用のシステムを標的にします。セキュリティ専門家は「パッチか回避策を48時間以内に適用すること」を推奨していますが、実際にはこの理想と現実の間に大きなギャップが存在しています。
オープンソースVPNと商用VPNの脆弱性比較
VPN製品は大きく分けて、オープンソースと商用の2種類があります。セキュリティの観点では、どちらにも一長一短があります。
オープンソースVPNはコードが公開されているため、理論的には多くの目で検証されることでセキュリティ品質が高まる可能性があります。一方で、脆弱性が発見された場合、その情報も公開されやすく、攻撃者が悪用するリスクが高まります。
商用VPNは専門のセキュリティチームによる開発・検証が行われる利点がありますが、クローズドなプロセスであるため、未発見の脆弱性が潜在している可能性もあります。また、ベンダーの対応速度や透明性にも差があり、製品選定の際には注意が必要です。
在宅勤務の普及でさらに露呈したVPNの限界
リモートワーク急増によるVPNキャパシティ問題と応急処置の危険性
コロナ禍による急激なリモートワークの拡大は、従来は一部の従業員のみが利用していたVPNシステムに想定外の負荷をかけました。この状況に対応するため、多くの企業が緊急的にVPNの増強や認証要件の簡略化などの応急処置を実施しています。こうした対応はセキュリティ要件を犠牲にする形で行われることが多く、結果として攻撃者に新たな侵入経路を提供することになります。
私物デバイスからのアクセスによるセキュリティ境界の曖昧化
リモートワークの増加に伴い、企業管理下にないBYODからのVPN接続も急増しました。これらの私物デバイスは企業のセキュリティポリシーに準拠していないことが多く、マルウェア感染や脆弱性のあるソフトウェアなどのリスクを企業ネットワークに持ち込む可能性があります。VPNが前提とする「信頼できる端末からのアクセス」という想定が崩れ、セキュリティ境界が曖昧になる問題を引き起こしています。
エンドポイントセキュリティの管理が困難になる問題
在宅勤務環境では、社内ネットワーク内で機能していたファイアウォールやIDS/IPSなどの集中型セキュリティ対策がバイパスされる形となります。その結果、各エンドポイント自体のセキュリティが重要性を増していますが、リモート環境下での端末管理やセキュリティパッチの適用状況確認は格段に困難です。社内と比較して脆弱な環境からのアクセスを受け入れざるを得ないという、VPNの設計思想における根本的な矛盾が表面化しています。
【事例から学ぶ】VPNが起因となった実際のサイバー攻撃
VPNの脆弱性を悪用したサイバー攻撃は年々増加しており、その影響は個人ユーザーから大企業、政府機関まで広範囲に及んでいます。以下では、実際に発生したVPN関連の主要なサイバー攻撃事例を詳しく見ていきます。
大阪急性期・総合医療センターのVPN脆弱性を突いたランサムウェア被害事例
攻撃経路と侵入手法
攻撃者は、給食事業者のシステムを足がかりとして病院のネットワークに侵入しました。侵入経路となったのは2021年に脆弱性が公表されていたVPN機器でした。病院と給食事業者はRDPで常時接続されており、攻撃者はこの接続を通じて病院内システムに侵入し、院内全体へ感染を拡大させました。
被害の規模
被害の規模は甚大で、院内の約2300台のサーバー/端末のうち約1300台がランサムウェア「Phobos」の亜種に感染しました。また、電子カルテシステムの1次・2次バックアップ、さらにはLTOテープの第1世代バックアップまでもが感染するという深刻な状況に陥りました。
最も重大な問題は、電子カルテが使用できなくなったことで、院内業務は紙の診療録による代行を余儀なくされました。これにより診療情報の共有や保管、管理などで現場は混乱し、病院機能に深刻な支障が生じました。
発覚した脆弱性と対策
インシデント調査により、以下のセキュリティ上の問題点が明らかになりました。
- 電子カルテのパスワードが導入当初から簡易的なもので、全職員が同一パスワードを使用
- 全職員が管理者権限でサーバーを操作できる状態だった
- アンチウイルスが未設定のサーバーが存在
- 民生品のルーターやサポート切れのWindows OSが使用されていた
これらの問題を受けて以下の対策が実施されました。
- パスワードを16文字以上に強化
- 15分以上の未操作でアカウントロックを実行
- サーバー/ユーザーIDごとに異なるパスワードを設定
- 多層防御アプローチの導入
- バックアップ運用の見直し
- IT資産管理システムの導入
- サイバー攻撃対応手順の策定
- 「医療情報システム安全管理委員会」の設置
この事例は、VPN脆弱性の放置が引き起こす潜在的なリスクの大きさを如実に示しています。特に医療機関のような重要インフラでは、システム停止が人命に関わる可能性もあり、適切なセキュリティ対策の重要性を改めて認識させる事例となりました。
参考:病院に逸失利益が数十億円規模の影響与えたランサムウェア攻撃の実際と対応策 - DIGITAL X(デジタルクロス)
JAXA(宇宙航空研究開発機構)のVPN脆弱性を起点とした不正アクセス事例
攻撃経路と侵入手法
攻撃者は、JAXAが使用していたVPN装置の公表済み脆弱性を悪用して侵入を開始しました。その後、サーバーへの侵入→アカウント情報の窃取→Microsoft 365への不正アクセスという流れで攻撃が拡大しました。特筆すべきは、未知のマルウェアが使用され侵害の検知が困難だった点です。
被害の規模
本インシデントにより、JAXAの端末・サーバーに保存されていた一部の情報(JAXA職員等の個人情報を含む)が漏洩した可能性が確認されています。さらに、Microsoft 365上でJAXAが管理していた情報の一部(外部機関と業務を共同で実施するにあたっての情報及び個人情報)が漏洩したことも確認されました。
JAXAの発表によれば、ロケットや衛星の運用等の機微な情報は侵害を受けたシステムでは扱われておらず、国内外の関係機関との協力を含め、事業遂行が困難になるような深刻な影響は生じていないとしています。
発覚した脆弱性と対策
インシデント調査の過程で、主に以下の問題点が明らかになりました:
- VPN装置の脆弱性管理の不備(パッチ適用の遅延)
- 未知のマルウェア検知体制の不足
- クラウドサービスのアカウント保護不足
- 内部ネットワークの不適切なセグメンテーション
これらに対し、パッチ適用プロセスの改善、監視体制の強化、外部接続方法の見直し、多要素認証の強化などの対策が実施されました。
この事例は、政府系研究機関であっても既知のVPN脆弱性を起点とした侵入が発生しうることを示しており、継続的な脆弱性管理と監視体制の重要性を改めて浮き彫りにしています。特に国家の宇宙開発を担う重要機関において、こうした情報漏洩が発生したことは、あらゆる組織においてVPNセキュリティを再検討する必要性を強く示唆しています。
参考:JAXA | JAXAにおいて発生した不正アクセスによる情報漏洩について
VPN安全性強化のための実践的対策
VPNを利用し続ける企業にとって、そのセキュリティを強化することは喫緊の課題です。以下では、VPN環境のセキュリティを強化するための実践的な対策を詳しく解説します。
VPN利用継続時に最低限実施すべき強化策
VPNアプライアンスの定期的な脆弱性チェックとパッチ適用体制
VPN製品の脆弱性は常に発見され続けているため、定期的な脆弱性チェックとパッチ適用は最も基本的かつ重要な対策です。以下のような体制構築が推奨されます。
- 脆弱性情報の収集体制の確立
JVN、US-CERTなどの脆弱性情報ソースの定期確認や、ベンダーからのセキュリティアドバイザリの購読
- パッチ適用の優先度判断プロセスの確立
影響度と緊急度に基づく適用判断基準の明確化
- 計画的なパッチ管理
通常のメンテナンスサイクルと緊急時の特別対応手順の策定
- パッチ適用前後の検証プロセス
適用による影響評価と、適用後の動作確認手順の標準化
特に重要なのは、クリティカルな脆弱性に対しては48時間以内にパッチを適用するといった明確なSLAを設定することです。また、パッチ適用が遅れる場合の代替緩和策(WAF設定や特定IPからのアクセス制限など)も事前に検討しておくべきです。
多要素認証と高度なアイデンティティ管理の導入
VPNアクセスに対する多要素認証(MFA)の導入は、認証情報漏洩のリスクを大幅に低減します。特に以下の点に注意して実装することが重要です。
- すべてのVPNユーザーに対するMFAの必須化
パスワードだけでなく、追加の認証要素による不正アクセスの防止
- リスクベース認証の導入
アクセス元の場所や時間、デバイスの状態などに基づいた認証強度の動的調整
- シングルサインオン(SSO)との統合
認証プロセスの簡素化と一元管理の実現
- 特権アカウント管理
管理者アカウントに対する厳格な認証と監査の実装
また、定期的なパスワード変更やパスワード強度ポリシーの適用だけでなく、パスワードレス認証(生体認証やセキュリティキーなど)の導入も検討すべきです。これにより、フィッシング攻撃によるパスワード漏洩のリスクを大幅に低減できます。
ネットワークセグメンテーションによるアクセス範囲の制限
VPNを通じたアクセスの範囲を必要最小限に制限するためのネットワークセグメンテーションは、侵害時の被害を局所化する上で非常に効果的です。
- 最小権限の原則に基づいたVPNアクセスポリシーの設定
必要な機能へのアクセスのみを許可し、不要な権限を排除
- ロールベースのアクセス制御
ユーザーの役割に応じた適切なネットワークセグメントへのアクセス制限
- マイクロセグメンテーション
従来の大きなセグメント分けではなく、より細かな単位でのアクセス制御
- ゼロトラストアーキテクチャの要素取り入れ
ネットワーク位置に関わらず、すべてのアクセスを常に検証
特に効果的なのは、VPNユーザーごとに「許可リスト(ホワイトリスト)」を作成し、明示的に許可されたシステムやサービスにのみアクセスできるよう制限することです。これにより、VPN認証が突破されたとしても、攻撃者の行動範囲を大幅に制限することができます。
VPNログモニタリングと異常検知の重要性
効果的なVPNログの収集・分析・監視方法
VPNログの適切な収集と分析は、不正アクセスの早期発見と対応に不可欠です。
- 集中型ログ管理の実現
すべてのVPNログを一元管理するSIEM(Security Information and Event Management)システムの導入
- ログ保持期間の適切な設定
少なくとも90日以上、理想的には1年間のログ保持
- 包括的なログ収集
認証成功/失敗、セッション開始/終了、接続元IP、アクセスしたリソースなど、詳細なログ項目の収集
- リアルタイム分析とアラート設定
重要イベントに対する即時アラートの設定
また、ログデータの改ざん防止のため、ログの暗号化や書き込み専用ストレージの使用なども検討すべきです。さらに、ログフォーマットの標準化により、複数のセキュリティシステムからのログを統合分析することで、より包括的な脅威検知が可能になります。
異常な接続パターンを検出するためのベースライン確立
通常の接続パターンを把握し、異常を検出するためのベースライン確立は、高度な脅威検知の基盤となります。
- ユーザー行動分析(UBA)の導入
個々のユーザーの正常な行動パターンを学習し、逸脱を検知
- 時間帯別・曜日別のアクセスパターン分析
通常の業務時間外のアクセスや、休日のアクセスといった異常を検出
- 地理的アクセスパターンのモニタリング
普段と異なる地域からのアクセス試行の検知
- アクセス頻度や転送データ量の監視
通常より高頻度のアクセスや大量データ転送の検知
これらのベースラインを確立するためには、まず1〜3ヶ月の学習期間を設け、その後も継続的に更新していくことが重要です。また、季節変動や業務サイクルなどの正当な変化要因も考慮する必要があります。
VPNのセキュリティリスクを克服する - データレスクライアントという選択肢
VPNの構造的な限界を根本的に解決するためには、従来の境界型セキュリティモデルからの脱却が必要です。ここでは、新たなアプローチとしてのデータレスクライアントについて詳しく解説します。
VPNとデータレスクライアントのセキュリティモデル比較
VPNとデータレスクライアントは、根本的に異なるセキュリティ哲学に基づいています。それぞれの特徴を比較してみましょう。
保護の焦点の違い
VPNは「ネットワーク保護型セキュリティ」を採用しています。つまり、企業のネットワークへの入口を保護し、その内部では比較的自由なアクセスを許可するモデルです。これは「城壁と堀」型セキュリティとも呼ばれ、境界の防御に重点を置いています。
一方、データレスクライアントは「データ保護型セキュリティ」を採用しています。データそのものを保護する方式で、企業の機密情報がエンドポイント(クライアント端末)に残らない設計となっています。これは「データを端末に残さない」というアプローチとも言え、情報漏洩リスクを根本から低減します。
脅威シナリオに対する耐性の違い
VPNモデルでは、以下のような脅威シナリオに対して脆弱性があります。
- VPN認証情報漏洩時
内部ネットワーク全体がリスクにさらされる
- 端末紛失・盗難時
端末に保存されたデータや認証情報が露出するリスク
- マルウェア感染時
感染端末から内部ネットワークへの攻撃拡大のリスク
対してデータレスモデルでは、認証情報漏洩、端末紛失・盗難、マルウェア感染のいずれの場合でも、データが端末に残らず業務環境が隔離されているため、被害範囲を最小限に抑えることができます。アクセス権限も厳密に制限され、セッション終了後にはデータ痕跡が残りません。
アーキテクチャ上の本質的差異
VPNは「信頼の境界」を設定し、その内側は比較的オープンなアーキテクチャです。これは導入が容易である一方、一度境界が突破されると内部での防御が難しいという弱点があります。
データレスクライアントは「ゼロトラスト」の原則に基づいており、場所や接続形態に関わらず、常に検証を行います。また、データをエンドポイントに残さないため、端末のセキュリティ状態に依存するリスクが低減されます。
VPNの安全性課題を直接解決するデータレスクライアントの特長
単一障害点問題の解消
VPNの大きな課題の一つは、VPNゲートウェイが単一障害点となることでした。攻撃者がこの一点を突破すれば、内部ネットワーク全体が危険にさらされる可能性があります。データレスクライアントでは、この問題に対して根本的に異なる設計思想を採用しています。アクセス制御がよりきめ細かく分散化されており、一箇所の障害が全体に影響するリスクが大幅に低減されています。
また、従来のVPNでは全てのトラフィックが一つのゲートウェイを通過する必要がありましたが、データレスクライアントではクラウドサービスへの直接アクセスと組み合わせることで、より効率的かつ安全なアクセスモデルを実現できます。これにより、単一のボトルネックが存在しない、より堅牢なセキュリティアーキテクチャが構築可能になります。
過剰なアクセス権限問題の解決
VPNの「過剰な信頼性」の問題は、データレスクライアントのアクセス制御モデルで根本的に解決されます。従来のVPNでは認証に成功すると広範なネットワークアクセスが許可されていましたが、データレスクライアントでは、より細かく厳格なアクセス制御が実現されています。このアプローチには以下のような特徴があります。
- アプリケーションレベルのアクセス制御
ネットワークレベルではなく、個別のアプリケーションやデータに対するきめ細かいアクセス制御
- コンテキストベースのアクセス判断
ユーザー、デバイス、場所、時間などの要素を総合的に評価
- 継続的な再認証
セッション中も定期的に権限を再評価
これにより、「最小権限の原則」を厳格に適用でき、攻撃者の行動範囲を大幅に制限することができます。
エンドポイントセキュリティの脆弱性対策
VPNモデルでは、エンドポイントのセキュリティ状態が内部ネットワーク全体のリスクに直結していました。端末がマルウェアに感染していれば、VPN接続を通じて内部ネットワークにも影響が及ぶ可能性があります。
データレスクライアントでは、エンドポイントセキュリティに対するアプローチが根本的に異なります。端末自体のセキュリティ状態に依存せず、以下のような機能によってリスクを大幅に低減します。
- 隔離された業務環境
個人利用の環境と業務環境が完全に分離され、相互の影響を防止
- データの非保存
端末にデータを保存しないため、端末の紛失・盗難時のリスクを最小化
- 一時的なセッション
業務終了後は環境が完全に消去され、痕跡が残らない設計
- デバイスの状態確認
アクセス時にデバイスの健全性を評価し、リスクの高い端末からのアクセスを制限
このアプローチにより、エンドポイントに対する信頼度を下げつつも、安全な業務環境を提供することが可能になります。従来のVPNが「信頼できるデバイス」を前提としていたのに対し、データレスクライアントは「デバイスを信頼しない」前提で設計されており、ゼロトラストの理念により適合しています。
VPNの安全性を見直す - リスクを正しく理解し最適な選択を
VPNは依然として多くの企業で利用されていますが、様々な脆弱性とリスクを抱えています。単一障害点となる危険性や内部ネットワークへの過度なアクセス権限付与など、根本的な設計上の問題は、パッチ適用だけでは解決できません。今後は、ゼロトラストセキュリティモデルへの移行を視野に入れ、データレスクライアントなどの次世代技術の導入を検討することが重要です。セキュリティ対策は「完全な解決策」ではなく「継続的な進化」であることを理解し、常に最新の脅威情報と対策技術をキャッチアップしていきましょう。
この進化の道筋において、有効な選択肢となるのがデータレスクライアントです。例えば「セキュアコンテナ」なら、端末内に隔離されたセキュアな業務領域を生成し、その中でのみ業務を行うことができます。これにより端末内に業務データを残すことなく高度なセキュリティを実現します。業務終了時にはこの領域を完全に削除するため、MDMの導入やリモートワイプといった追加対策がなくても、万が一端末の紛失や盗難が発生した場合でも重要なデータが漏洩する心配がありません。さらに、スマートフォンやタブレットからのセキュアブラウザによる作業にも対応しているため、デバイスを問わない多様な働き方にも柔軟に対応できます。VPNの課題を解決しながら、より高度で使いやすいセキュリティ環境を構築する第一歩として、ぜひご検討ください。
CACHATTO Oneに関する資料請求やお問い合わせはこちら。
お気軽にお問い合わせください!
リモートアクセスや製品に関する
お役立ち資料をご用意しています。
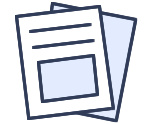 お役立ち資料ダウンロード
お役立ち資料ダウンロード
リモートアクセスや製品に関する
様々なご質問にお答えします。
 メールでお問い合わせ
メールでお問い合わせ