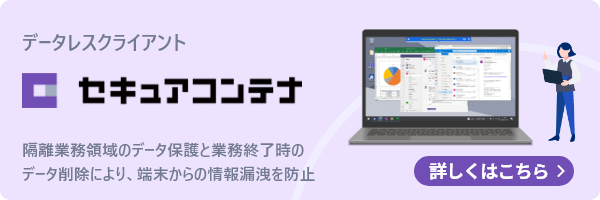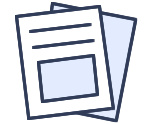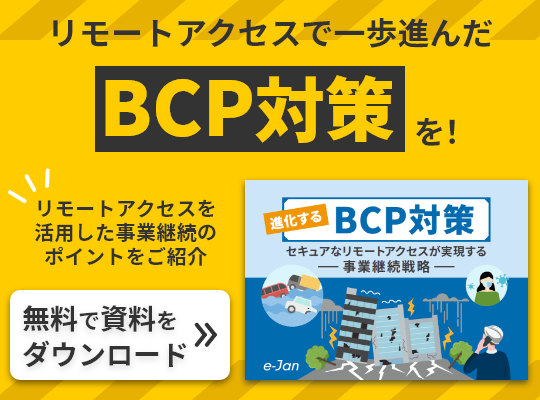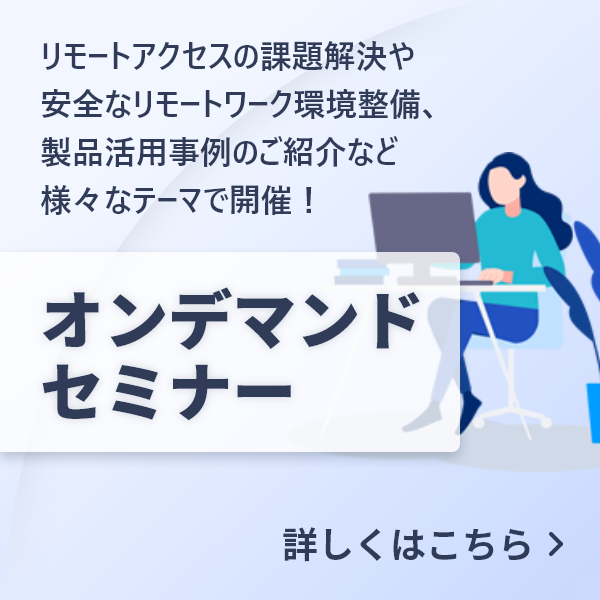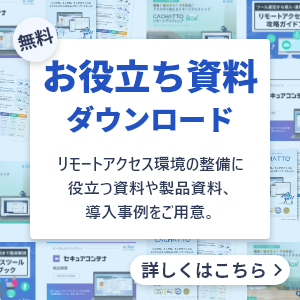BCP対策にクラウドを活用すべき理由とは?コスト削減と事業継続性の実現
2025.07.30投稿、2025.07.30更新
ビジネスのデジタル化が進み、多くの企業でクラウドサービスの活用が当たり前となっている今、改めてBCP対策の観点からクラウドの価値を見直す動きが広がっています。「既存のクラウド環境を、どのようにBCP対策に活かせるのか」「追加で何を準備すべきか」多くの企業が、このような検討段階にあるのではないでしょうか。
近年の自然災害の増加や、予期せぬパンデミックなどを経験する中で、クラウドの活用方法をBCP対策の視点で見直すことは、ビジネスの継続性を確保する上で重要な課題となっています。
本記事では、既存のクラウド環境を活用したBCP対策の設計戦略から、実装における注意点、さらには最新のソリューションまでを詳しく解説します。
企業のBCP対策におけるクラウド活用のメリット
バックアップ環境の維持に莫大なコストと運用負荷がかかる従来型のBCP対策に対し、クラウドを活用することで柔軟かつ効率的な事業継続性の確保が実現できます。
従来型のBCP対策が抱える課題と限界
従来型のBCP対策とは、主にオンプレミス環境を前提とした対策を指します。具体的には、バックアップサイトとしての予備のデータセンターの確保や、テープバックアップによるデータ保全、専用線による冗長化など、物理的な設備投資を中心とした方法です。
このような従来型でのBCP対策には、大きく3つの課題があります。まず、バックアップサイトの確保と維持に莫大なコストがかかります。災害時に確実に機能するためには、地理的に離れた場所に同等の設備を用意する必要があり、その設備は普段はほとんど使用されないにもかかわらず、継続的な保守と運用が必要となります。
次に、システムやデータの更新に応じて、バックアップ環境も同期して更新する必要があるため、運用負荷が高くなります。特に、システムの更新や変更が頻繁に発生する現在のビジネス環境では、この運用負荷は無視できない課題となっています。
さらに、災害時の復旧手順が複雑で、実際の災害時に計画通りに機能するか不透明な点も課題です。特に大規模災害時には、担当者の参集自体が困難になる可能性もあり、人的依存度の高い復旧手順では確実な事業継続が望めません。
クラウドベースBCP対策の特徴と利点
このような従来型の課題に対し、クラウドの特性を活かしたBCP対策は、より効率的で効果的な事業継続性の確保を可能にします。クラウドベースのBCP対策には、以下のような特徴と利点があります
コストと運用負荷の最適化
- 平常時は最小構成で運用し、必要時のみリソースを拡張可能
- バックアップサイトの物理的な保守・運用が不要
- 自動化による運用負荷の大幅な軽減
高い柔軟性と可用性
- リージョン間でのシステム冗長化が容易
- 災害時の負荷増大にも自動的にスケールアウト対応が可能
- 地理的分散が容易で、広域災害にも対応可能
運用の確実性向上
- 自動化された復旧手順により人的依存度を低減
- 定期的な切り替えテストが容易
- クラウドベンダーによる継続的な機能向上とセキュリティ強化
しかし、これらの利点があるにもかかわらず、多くの企業ではクラウドの特性をBCP対策に十分活用できていないのが現状です。例えば、クラウドの標準機能として提供されているリージョン間レプリケーションやオートスケーリング機能を使用していない、災害時の切り替え手順が整備されていない、あるいはマルチクラウド環境でのデータバックアップ戦略が確立されていないといった課題が見られます。これらの機能を適切に活用することで、より強固なBCP対策を実現できます。
クラウドを活用したBCP対策の設計戦略
クラウドのメリットを最大限に活かすには、適切な設計と計画が不可欠です。マルチクラウド環境の構築からバックアップ体制の確立まで、効果的な設計のポイントを解説します。
マルチクラウド・分散化戦略の設計
クラウドを活用したBCP対策を効果的に実装するには、単一のクラウドサービスに依存せず、複数のクラウドを組み合わせた分散化戦略が重要です。主要なクラウドプロバイダが提供する複数のリージョンを活用し、地理的に離れた場所にワークロードを分散させることで、災害時の影響を最小限に抑えることができます。また、各クラウドプロバイダの強みを活かしたサービス選択を行うことで、ベンダーロックインのリスクを軽減しながら、コストパフォーマンスに優れたリソース配置が可能となります。
データバックアップとリカバリー計画の策定
クラウド環境におけるデータバックアップとリカバリーでは、クラウドサービスの特性を活かした効率的な計画が重要です。スナップショット機能やクロスリージョンレプリケーションなど、クラウド特有のバックアップ機能を活用することで、より柔軟で効率的なデータ保護が実現できます。また、データの重要度に応じて保存場所を選択し、自動復旧スクリプトの準備やクラウドサービス間のデータ同期方法を確立することで、迅速な復旧が可能となります。特に、復旧優先順位に基づいたワークフローを事前に設計しておくことで、災害時の混乱を最小限に抑えることができます。
システム切り替えの自動化と運用設計
クラウドサービス間のシステム切り替えを効率的に行うためには、自動化された運用設計が不可欠です。ヘルスチェックに基づく自動フェイルオーバーや、ロードバランサーを活用した負荷分散、DNSを活用した経路制御の自動化など、クラウドサービスが提供する機能を最大限に活用します。また、クラウド横断的な統合監視の実装やアラート基準の標準化、インシデント発生時の対応フローを整備することで、迅速かつ確実な切り替えが可能となります。これらの仕組みを適切に設計・実装することで、災害時でも人的操作を最小限に抑えた自動的な対応が可能となります。
クラウドベースBCP対策における注意点とリスク対策
クラウド環境特有のセキュリティ、コスト管理、法規制対応など、考慮すべき重要な観点について解説します。
セキュリティリスクとその対応策
クラウド環境でのBCP対策においては、従来型とは異なるセキュリティリスクへの対応が必要です。特に、複数のクラウドサービスを連携させる際のセキュリティ確保が重要となります。マルチクラウド環境での認証統制や、クラウド間でのデータ転送時の暗号化、アクセス権限の一元管理など、包括的なセキュリティ体制の構築が求められます。
また、システムを地理的に分散させることで生じる固有のリスクにも注意が必要です。各リージョンの法規制に対応しつつ、セキュリティポリシーを統一的に適用し、インシデント検知・対応を一元化することで、分散環境特有のリスクを最小限に抑えることができます。
コスト管理と最適化の進め方
BCP対策におけるクラウドコストを適切にコントロールするためには、平常時と災害時それぞれの状況に応じた管理方法が重要です。平常時は、リソースの自動スケーリング設定を活用し、待機系システムを最小構成に維持することでコストを抑制します。例えば、バックアップデータの保持期間の最適化や、非稼働時間帯でのインスタンス停止など、きめ細かな運用設定により、従来型の専用環境と比較してコスト削減が期待できます。
一方、災害時には、事業継続に必要なリソースを適切に拡張する必要があります。この際、あらかじめ設定したコストの上限値やアラートを活用し、予算超過を防ぎます。具体的には、月間予算の設定、リソース使用量の上限設定、急激なコスト増加時のアラート通知など、複数の管理策を組み合わせることで、予期せぬコスト増大を防ぐことができます。また、定期的なコスト分析レポートの確認により、最適化の余地がある部分を特定し、継続的な改善を図ることが重要です。
法規制とコンプライアンスへの対応
クラウド環境でのBCP対策では、データの保管場所に関する法的要件の確認や、監査証跡の確保、プライバシー保護規制への対応など、様々な法規制への準拠が求められます。これらの要件に対応するため、定期的な準拠性評価の実施や、規制変更への迅速な対応体制の整備が必要です。特に、第三者監査への対応準備も含めた包括的なコンプライアンス体制の構築が重要となります。
クラウド環境のレジリエンスを高める最新ソリューション
ゼロトラストセキュリティやAIの活用など、クラウドベースのBCP対策をさらに強化する新しい取り組みを紹介します。
ゼロトラストセキュリティの実装とデータレスクライアントの活用
昨今のセキュリティ環境では、クラウドベースのBCP対策においてもゼロトラストアーキテクチャの採用が不可欠となっています。常時認証の実装や最小権限アクセスの徹底、振る舞い検知による異常検出など、より高度なセキュリティ対策が求められています。
特にエンドポイントセキュリティの強化において、データレスクライアントの導入は効果的な選択肢となります。セキュアなリモートアクセス環境の構築とデバイス認証の厳格化により、テレワーク環境下でも安全な業務継続が可能となります。
ゼロトラストやデータレスクライアントについては、次の記事も参考にしてください。
関連記事

ゼロトラストとは?メリットやデメリット、実現するためのポイントを紹介
関連記事

データレスクライアントとは?仕組みやVDIとの違い、メリット・デメリットを解説
AIを活用した予知保全と自動復旧
クラウドサービスで提供されるAI機能を活用することで、より高度なBCP対策が実現可能です。クラウドネイティブなAIを活用した異常検知の自動化や、障害予測による予防的メンテナンス、インシデント対応の自動化などにより、システムの可用性を高めることができます。
さらに、AI支援による運用効率化も進んでいます。復旧手順の最適化提案やリソース使用予測、セキュリティ脅威の早期発見など、AIの活用により、より効率的で効果的なBCP対策の実現が可能となっています。
クラウド活用とエンドポイントセキュリティの融合で実現する、強固なBCP対策
クラウド環境を活用したBCP対策は、既存のクラウドインフラを活かしながら、より強固な事業継続体制を構築できる有効な手段です。特に、マルチクラウド環境の活用によるリスク分散や、クラウドネイティブなAIを用いた予知保全の導入など、クラウドならではの特性を活かすことで、より柔軟で強靭なBCP体制を実現できます。
しかし、クラウドベースのBCP対策を確実に機能させるためには、セキュリティ面での配慮が欠かせません。特に、リモートワークが一般化した現在では、社外からのアクセスに対する包括的なセキュリティ対策が重要となっています。
この課題に対する効果的なソリューションとして、データレスクライアントの活用が注目されています。例えば、データレスクライアントである「セキュアコンテナ」なら、隔離されたセキュアな業務領域を生成し、その中でのみ業務を行うことができるため、端末内に業務データを残すことなく、高度なセキュリティを実現します。業務終了時にはその領域を削除するため、MDMの導入やリモートワイプを使用せずとも、万が一端末の紛失や盗難が発生した場合でも、重要なデータを失う心配がありません。さらに、スマートフォンやタブレットからのセキュアブラウザによる作業にも対応しているため、多様な働き方にも柔軟に対応できます。
このように、クラウドの特性を最大限に活かしながら、エンドポイントセキュリティも考慮した総合的なアプローチにより、より確実で実効性の高いBCP対策を実現することが可能となります。今後も、新たなテクノロジーやソリューションの登場により、クラウドを活用したBCP対策はさらに進化していくことでしょう。
併せて実装戦略をまとめたホワイトペーパー「進化するBCP対策 セキュアなリモートアクセスが実現する -事業継続戦略-」もぜひダウンロードしてご覧ください。
CACHATTO Oneに関する資料請求やお問い合わせはこちら。
お気軽にお問い合わせください!
リモートアクセスや製品に関する
お役立ち資料をご用意しています。
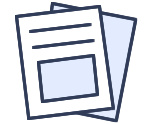 お役立ち資料ダウンロード
お役立ち資料ダウンロード
リモートアクセスや製品に関する
様々なご質問にお答えします。
 メールでお問い合わせ
メールでお問い合わせ