BCPの基本情報については、次の記事も参考にしてください。
関連記事
企業を取り巻く環境が急速に変化する中、自然災害やサイバー攻撃などのリスクは年々増加の一途をたどっています。そのため、事業継続の要となるITシステムのBCP対策は、企業の重要課題として認識されています。
本記事では、システム面でのBCP対策について、基本的な考え方から最新のソリューションまでを解説します。システム管理者として押さえるべき検討事項と対策の進め方をまとめています。
BCPの基本情報については、次の記事も参考にしてください。
関連記事

目次
企業のITシステムを脅かすリスクは多様化・深刻化の一途をたどっており、組織的なBCP対策の確立が急務となっています。
近年、自然災害の発生頻度は増加傾向にあり、2024年だけでも日本国内で複数の大規模地震や豪雨災害が発生しています。これらの災害は、企業のITシステムに深刻な影響を及ぼす可能性があり、特にデータセンターやサーバールームの物理的な損壊、電力供給の停止、通信インフラの寸断の発生は、事業継続に直接的な影響を与える重大なリスクとなっています。
さらに、サイバーセキュリティの脅威も年々深刻化しています。ランサムウェア被害は過去最多を記録し、その攻撃手法も高度化・巧妙化が進んでいます。特に注目すべきは、単なるデータの暗号化にとどまらず、機密情報の窃取や公開を脅す二重脅迫型の攻撃が主流となっていることです。
これらの脅威に対して、従来型の個別対策だけでは不十分です。増大する脅威に効果的に対応するためには、システムの可用性確保、データ保護、セキュリティ対策を統合的に捉える必要があります。単独の対策ではなく、これらの要素を包括的に組み込んだBCP対策の構築が重要となっています。
効果的なBCP対策を実現するためには、以下のような要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たすためには、システムの設計段階から包括的な対策を講じる必要があります。重要業務の特定から具体的なシステム構成の検討まで、段階的かつ計画的なアプローチが求められます。
重要業務の特定やリスクアセスメントから、システムアーキテクチャ、データバックアップまで、BCP対策に必要な設計上の考慮ポイントを解説します。
BCP対策の第一歩は、組織にとって重要な業務とそれを支えるシステムの特定です。業務の優先度評価では、収益への影響度や顧客サービスへの影響、法規制上の要件などを総合的に判断する必要があります。さらに、システムの重要度を分類する際は、業務停止時の許容時間やデータ損失の許容範囲、代替手段の有無などを詳細に検討します。
特に注意すべき点は、システム間の依存関係の把握です。クラウドサービスの利用が一般的となった現在、単一システムの評価だけでは不十分です。連携するサービスも含めた包括的な評価を行い、システム全体としての脆弱性を特定することが重要です。
加えて、サプライチェーンに関するリスク評価も重要です。システム部品の調達や保守サービスの継続性について、特定のベンダーへの依存度を評価し、必要に応じて代替調達先を確保することが求められます。特に重要なシステムについては、マルチベンダーでの構成を検討し、特定ベンダーの障害がシステム全体に波及するリスクを軽減することも有効です。
システムの可用性を高めるためには、適切なアーキテクチャ設計が不可欠です。システムの冗長化設計は、可用性向上の基本となります。サーバーやネットワーク機器の二重化、地理的に分散したデータセンターの活用、負荷分散による処理の分散化などにより、システム全体の耐障害性を向上させることができます。
障害対策の面では、単一障害点(SPOF)の排除が重要です。システムの各コンポーネントについて、その障害が全体に与える影響を評価し、必要に応じて自動フェイルオーバーの実装や監視・通知システムの整備を行います。また、復旧性を考慮し、システムのモジュール化や復旧手順の標準化、テスト環境の整備なども計画的に進める必要があります。
効果的なデータバックアップ戦略は、以下の3つの方式を適切に組み合わせることで実現できます。
これらの方式は、データの重要度と更新頻度に応じて使い分けることが重要です。また、バックアップデータの保管場所については、オンサイト、オフサイト、クラウドなど、複数の選択肢を組み合わせることで、災害時でもデータにアクセスできる体制を整えることができます。
さらに、バックアップデータの定期的な復旧テストも重要です。リストア手順を文書化し、実際に復旧できることを確認するとともに、アクセス権限の管理も適切に行う必要があります。これらの要素を組み合わせることで、より強固なBCP対策の基盤を構築することができます。
こうした基本的な設計・構成をベースとしながら、近年では様々な最新テクノロジーを活用したソリューションも登場しています。これらの新しい技術を活用することで、さらに効果的なBCP対策の実現が可能となってきています。
クラウドDR、データレスクライアント、リモートワーク環境など、BCP対策を強化する最新のシステムソリューションを紹介します。
事業継続に向けた災害対策として、クラウドベースのディザスタリカバリ(DR:災害復旧)システムの導入が広がりつつあります。災害やシステム障害が発生した際でも、業務を速やかに復旧できるよう、地理的に離れた複数のデータセンターにシステムやデータを分散して保管するソリューションが提供されています。
例えば、メインのシステムが地震や火災などで使用できなくなった場合でも、別の地域のバックアップシステムに自動的に切り替わることで、業務への影響を最小限に抑えることができます。また、これらのクラウドサービスは、通常時は必要最小限のリソースで運用し、実際に災害が発生した際には迅速にシステムリソースを拡張できる柔軟な構成となっているため、コストを抑えながら効果的な災害対策を実現できます。
リモートワークの普及により、エンドポイントセキュリティの重要性は一層高まっています。従来のVPNやMDMによる対策では、端末紛失時のリスクや運用負荷の高さが課題となっていました。
この課題を解決する手段として、データレスクライアントの活用が注目されています。データレスクライアントは、端末内に業務データを残さない仕組みで、隔離された安全な業務領域で作業を行い、セッション終了時にはその領域が完全に削除されるため、端末の紛失や盗難が発生しても、重要なデータが漏洩するリスクを最小限に抑えることができます。
MDMやデータレスクライアントについては、次の記事も参考にしてください。
関連記事

リモートワーク環境のセキュリティ確保には、包括的なソリューションの導入が有効です。多要素認証システムや、シングルサインオン(SSO)の仕組みを備えた認証基盤の導入により、セキュリティレベルを保ちながら利便性の高い環境を実現できます。
また、セキュアブラウザを活用することで、PCだけでなく、スマートフォンやタブレットからも安全に業務システムにアクセスできるようになります。これにより、デバイスを問わない柔軟な働き方を実現しながら、セキュリティリスクを最小限に抑えることができます。
さらに、災害時の事業継続には、確実なコミュニケーション手段の確保が不可欠です。クラウドベースのコミュニケーションツールを活用し、社内外との連絡手段を複数確保することで、災害時でも確実な情報共有と意思決定が可能となります。特に、モバイル端末からのアクセスも考慮し、場所を問わない連絡体制の整備が重要です。
このように、適切なシステムソリューションを組み合わせることで、より強固なBCP対策を実現できます。ただし、これらのソリューションを効果的に機能させるためには、適切な運用管理体制の整備が不可欠です。
多要素認証やシングルサインオンについては、次の記事も参考にしてください。
関連記事
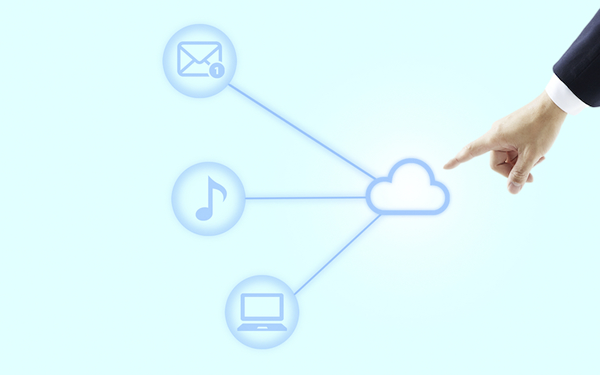
導入したソリューションを効果的に機能させるため、定期的な訓練・評価の実施、インシデント対応手順の整備、BCPマニュアルの作成など、実効性の高い運用管理方法を説明します。
システム面でのBCP対策は、適切な運用とメンテナンスがあって初めて機能するため、定期的な訓練を通じて、システムの切り替えやバックアップからの復旧が確実に実行できることを確認する必要があります。
訓練の実施にあたっては、システム障害を想定したシナリオに基づき、バックアップシステムへの切り替えや、データ復旧の手順を実際に実施します。これにより、手順書の実効性を検証するとともに、担当者の習熟度を高めることができます。また、訓練の結果を評価し、必要に応じて手順や体制の見直しを行うことで、より実践的な対策へと改善を重ねることができます。
システム障害や災害が実際に発生した際の初期対応は、被害の拡大を防ぎ、早期復旧を実現するための重要な鍵となります。そのため、多くの組織では、インシデント対応を統括するCSIRT(Computer Security Incident Response Team)を設置し、システム障害やセキュリティインシデントの検知、分析、対応を一元的に管理する体制を整備しています。
CSIRTによる初期対応では、まず障害の影響範囲の特定と状況の正確な把握を最優先します。その上で、あらかじめ定められた判断基準に基づき、バックアップシステムへの切り替えなど、必要な対策を実行します。また、経営層や関係部門、お客様への適切な情報共有も、混乱を防ぐために重要な要素となります。こうした一連の対応手順を明確に定め、関係者間で共有しておくことで、迅速な意思決定と対策実施が可能となります。
BCP対策を確実に機能させるためには、システムの構成図や重要な設定情報、復旧手順など、必要な情報を漏れなく記載したマニュアルの整備が不可欠です。特に、システム間の依存関係や復旧時の優先順位については、明確な文書化が求められます。
ただし、システム環境は常に変化しているため、マニュアルの定期的な見直しと更新が欠かせません。システムの更新や設定変更が行われた際には、それに応じてマニュアルも更新し、常に最新の状態を保つようにします。また、訓練やインシデント対応から得られた知見もマニュアルに反映させることで、より実践的な内容へと改善を図ることができます。
さらに、定期的なシステム監査を通じて、BCP対策の実効性を客観的に評価することも大切な要素となります。監査では、システムの構成や設定が適切に文書化されているか、実際の運用が手順書通りに行われているか、また各種規制やコンプライアンス要件に適切に対応できているかを確認します。これらの監査結果をマニュアルの改善に活用し、PDCAサイクルを回していくことで、より強固なBCP体制を構築できます。
システム面でのBCP対策は、単なる災害対策から、ビジネス継続性を確保するための総合的な取り組みへと進化しています。今日の企業に求められるBCP対策では、適切なリスク評価、システム設計、運用体制の整備に加え、リモートワークを前提としたセキュリティ確保が不可欠です。実装戦略をまとめたホワイトペーパー「進化するBCP対策 セキュアなリモートアクセスが実現する -事業継続戦略-」もぜひダウンロードしてご覧ください。
特に、エンドポイントセキュリティの分野では、従来型のMDMによる端末管理から、よりセキュアで運用負荷の少ないソリューションへと移行が進んでいます。その代表的な例が、端末内にデータを残さない「データレスクライアント」の活用です。
例えばデータレスクライアントである「セキュアコンテナ」では、隔離されたセキュアな業務領域を生成し、その中でのみ業務を行うことができるため、端末内に業務データを残すことなく、高度なセキュリティを実現します。業務終了時にはその領域を削除するため、MDMの導入やリモートワイプを使用せずとも、万が一端末の紛失や盗難が発生した場合でも、重要なデータを失う心配がありません。さらに、スマートフォンやタブレットからのセキュアブラウザによる作業にも対応しているため、多様な働き方にも柔軟に対応できます。