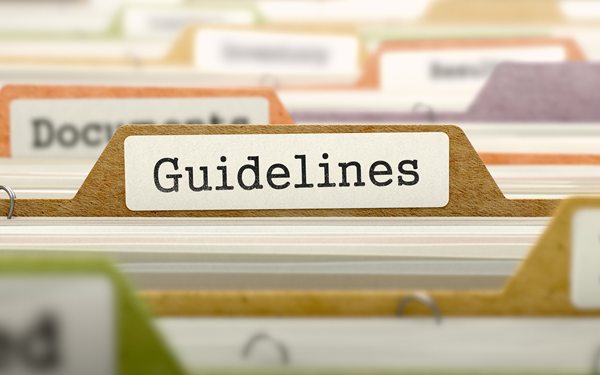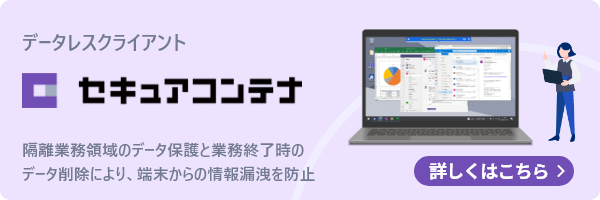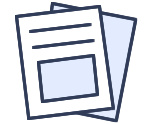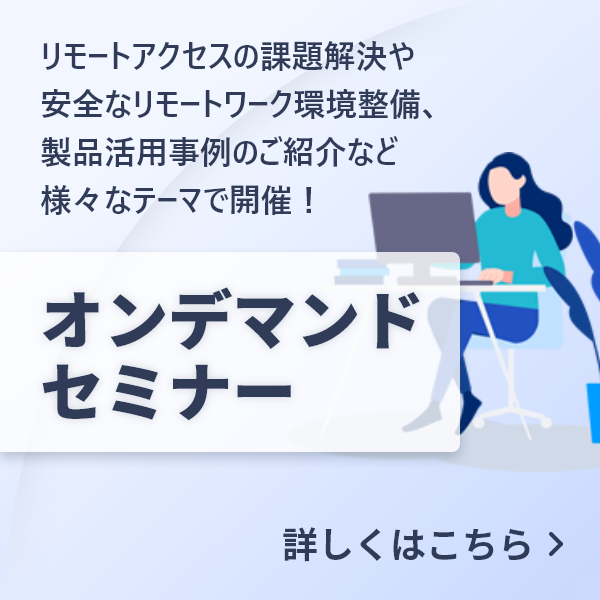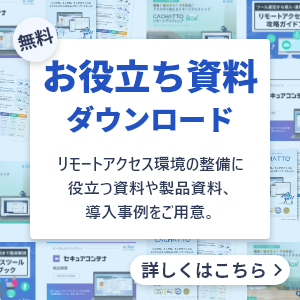テレワークガイドラインの実務ポイント:適切な労務管理とセキュリティ対策
2025.07.01投稿、2025.07.01更新
企業がテレワークを導入・運用する際の重要な指針となる厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」は、2021年3月の改定により、コロナ禍での経験を踏まえた内容へと更新されました。労働時間管理や人事評価、費用負担など、企業の実務担当者が直面する具体的な課題への対応方針が新たに示されています。
本記事では、改定されたガイドラインのポイントを整理するとともに、人事・総務部門における労務管理の実践方法から、IT部門が整備すべき情報セキュリティ対策まで、実務担当者が押さえるべき基本事項を解説します。
令和3年改訂テレワークガイドラインの基本
コロナ禍での経験を踏まえて改定された新ガイドラインでは、労働者と企業の双方にメリットをもたらす柔軟な働き方の実現を目指しています。ここでは、企業の実務担当者が押さえるべき基本的なポイントを解説していきます。
ガイドラインの目的と位置づけ
テレワークは、働く時間や場所を柔軟に活用できる働き方として注目を集めています。厚生労働省が策定したテレワークガイドラインは、企業がテレワークを導入・運用する際の実務指針として、労使双方にとって重要な意味を持っています。
このガイドラインは、労使双方のメリットを最大限に引き出しながら、適切な労務管理と労働者保護の両立を図ることを目的としています。事業者側には業務効率化による生産性の向上、育児や介護等を理由とした労働者の離職防止、優秀な人材の確保といったメリットがあります。一方、労働者にとっては、通勤時間の短縮による心身の負担軽減、仕事に集中できる環境での業務実施、育児や介護と仕事の両立といった利点があります。
ガイドラインでは、これらのメリットを安全に実現するため、テレワークを以下の3つの形態に分類して詳細な導入・運用方法を示しています。
-
在宅勤務
通勤を要せず、育児や介護との両立にも資する働き方
-
サテライトオフィス勤務
通勤時間を短縮しつつ、作業環境の整った場所で就労可能な働き方
-
モバイル勤務
労働者が自由に働く場所を選択でき、外勤の移動時間も有効活用できる働き方
そして、2021年3月の改定では、実務現場での課題に対応するため、以下の重要事項について明確な指針が示されました。
-
テレワークの対象業務や対象者の選定における公平性の確保
-
労働時間管理の適正な実施方法
-
人事評価における公平な取扱いの重要性
-
費用負担の取扱いに関する考え方
-
労働者の安全衛生の確保方法
導入・実施の基本枠組み
テレワークを円滑に導入・実施するためには、以下の5つの観点について、あらかじめ企業側と従業員で十分に話し合い、ルールを定めることが必要です。
-
導入目的の明確化
テレワーク導入の目的を、経営戦略の観点から明確に定める必要があります。業務効率化による生産性の向上はもちろん、優秀な人材の確保や離職防止、さらには従業員のワークライフバランスの実現など、企業と従業員双方にとってのメリットを考慮しましょう。
-
対象業務の選定
対象業務の選定では、「テレワークに向かない」という固定観念にとらわれず、業務の本質的な見直しを行うことが重要です。その上で、テレワーク可能な業務の範囲を設定し、オフィス勤務者との業務分担の考え方を整理します。
-
対象者の選定基準
雇用形態による不合理な差別を禁止し、公平性を確保することが必要です。特に、新入社員や異動直後の社員に対しては、円滑なコミュニケーションを確保するための特別な配慮が求められます。
-
実施場所等の基本ルール
在宅勤務やサテライトオフィス勤務など、実施場所ごとの選定基準を明確にします。その際、情報セキュリティの確保要件や作業環境整備の基準を具体的に定める必要があります。
-
導入に当たっての望ましい取組
ペーパーレス化の推進や決裁プロセスの電子化など、テレワークを前提とした業務プロセスの見直しが必要です。不必要な押印や署名の廃止も、円滑な業務遂行には欠かせません。
これらの基本的な枠組みを整備した上で、具体的な労務管理やセキュリティ対策を検討していくことが、テレワークの成功には不可欠です。また、導入後も継続的な見直しと改善を行うことで、より効果的な制度運営が可能となります。
労務管理の具体的な進め方
テレワークにおける労務管理では、適切な労働時間の管理と、公平な人事評価・費用負担の仕組みづくりが重要です。ガイドラインでは、これらの実務について具体的な指針を示しています。
労働時間管理の実務
社員の働く場所や時間が多様化する中、適切な労務管理を実現するため、テレワークでは以下の3つの労働時間制度から、企業の実態に合った制度を選択できます。
-
通常の労働時間制度
テレワーク中の従業員は、企業が就業規則で定めることにより、1日の所定労働時間を変更することなく、始業・終業時刻を柔軟に変更することができます。
-
フレックスタイム制
従業員が自らの裁量で始業・終業時刻を決定できる制度です。テレワーク時にはコアタイムを設けないなどの柔軟な運用が可能で、在宅勤務日とオフィス勤務日で労働時間を調整することもできます。
-
事業場外みなし労働時間制
労働時間の算定が難しい場合に適用できる制度で、所定労働時間働いたものとみなします。ただし、適用には一定の要件を満たす必要があります。
労働時間の把握方法としては、客観的な記録としてパソコンの使用時間等を活用する方法があります。また、従業員による自己申告も可能です。モバイルワーク等の場合は、事業場外みなし労働時間制の活用を検討することができます。
テレワーク特有の「中抜け時間」については、休憩時間や時間単位の年次有給休暇として扱うことが可能です。また、始業・終業時刻の間の時間から休憩時間を除いた時間を労働時間として取り扱うことも検討できます。
人事評価と費用負担
人事評価については、テレワークという新しい働き方に対応した評価基準の設定が求められています。特に、オフィスワーカーとテレワーカーの間で不公平が生じないよう、以下の点に留意が必要です。
-
評価の公平性確保
評価の公平性確保においては、テレワーク実施の有無によって評価上の不利益が生じないよう禁止するとともに、業務効率や成果に基づく公平な評価基準を設定する必要があります。また、これらの評価方法については、従業員に対して事前に十分な説明を行うことを求められます。
-
費用負担の明確化
費用負担の明確化については、通信費や情報通信機器等の費用負担の取り決めを行い、電気料金等の在宅勤務に伴う費用の取り扱いについても明確に定める必要があります。これらの費用負担に関する事項は、就業規則等での明文化が望ましいでしょう。
費用負担の具体例
・在宅勤務用のパソコン、周辺機器:企業が貸与
・通信回線利用料:実費や一定額を企業が負担
・消耗品費:業務に必要なものは企業が負担
このように基本的なルールを定めた上で、個々の状況に応じて柔軟に対応できる仕組みを整備することが望まれます。
安全衛生とセキュリティの確保
在宅勤務やモバイルワークが増える中、企業は従業員の安全衛生管理と情報セキュリティの両面で新たな課題に直面しています。ここでは、企業が整備すべきポイントを解説します。
労働安全衛生対策
テレワーク環境下での労働安全衛生対策として、作業環境整備が不可欠です。適切な照明、換気、作業姿勢に配慮した机や椅子の配置など、自宅での作業環境について具体的な指針を示す必要があります。また、長時間のPCワークによる身体的・精神的負担を軽減するため、定期的な休憩時間の確保や、ストレスチェックの実施などのメンタルヘルス対策も重要な要素となります。在宅勤務中の労働災害についても、その範囲や補償の仕組みを明確にし、従業員に周知することが求められます。
情報セキュリティ対策
情報セキュリティ対策では、まずリモートアクセスの安全性確保が重要です。VPNの利用や多要素認証の導入など、アクセス制御を適切に設定し、通信経路の暗号化を徹底します。情報漏洩防止については、データレスクライアントのような端末内に業務データを残さない仕組みの活用や、業務専用の隔離された作業領域の設定が有効です。特に私用端末を利用する場合は、業務データと私用データの明確な分離や、業務終了時のデータ消去を確実に行います。併せて、セキュリティインシデント発生時の報告体制や対応手順を整備し、従業員への周知を進めましょう。
データレスクライアントについては、次の記事も参考にしてください。
関連記事

データレスクライアントとは?仕組みやVDIとの違い、メリット・デメリットを解説
持続可能な制度運営の実現
テレワークを一時的な対応で終わらせず、企業の新しい働き方として定着させるためには、継続的な改善が欠かせません。効果的なコミュニケーション方法の確立や運用体制の整備など、長期的な視点で取り組むべきポイントを解説します。
教育訓練とコミュニケーション
テレワークの効果的な運用のためには、労働者と管理職双方への適切な教育が欠かせません。基本的なITスキルの習得支援やオンラインでのマネジメント手法の研修に加え、以下のような具体的な取り組みが効果的です。
- 定期的な1on1ミーティングの設定(週1回程度)
- チーム内での朝会や終礼のオンライン実施
- 業務の可視化ツール(プロジェクト管理ツール等)の活用
- オンライン上での雑談スペースの設置
- 新入社員等へのメンター制度の導入
- オンデマンド研修コンテンツの整備
- ハイブリッド形式での会議運営スキルの習得機会の提供
特にハイブリッド勤務の場合は、オフィスワークとテレワークを組み合わせる際の移動時間について、以下の基準で運用することが重要です。
- 従業員の自己都合による出社
通常の通勤時間として扱う
- 会社からの業務上の指示による出社
移動時間を労働時間として扱う
- 同日内でのオフィスワークとテレワークの切り替え時
原則として休憩時間として取り扱う
運用体制の整備
持続可能なテレワーク制度の運営には、人事部門、IT部門、総務部門など、関連部署間の緊密な連携が不可欠です。定期的な実態調査を通じて課題を把握し、改善策を検討・実施する体制を構築します。特に以下の点に注意を払います。
- 部門間連携による効果的な問題解決の仕組みづくり
- オフィスワーク・テレワーク双方での公平な評価基準の設定
- 勤務形態による不利益が生じないための評価者訓練の実施
- 社会情勢や技術革新に応じて柔軟に制度を見直せるよう、継続的な改善の仕組みを整備
このように、教育訓練・コミュニケーション面の具体策と、運用体制の整備の両面から、持続可能なテレワーク環境の実現を図ります。
持続可能なテレワーク環境の実現に向けて
テレワークガイドラインは、コロナ禍での経験を踏まえ、労務管理から情報セキュリティまで、実務に即した包括的な指針を示しています。人事評価の公平性確保や費用負担の明確化、労働時間管理の適正化など、企業が直面する具体的な課題への対応方針を明確にすることで、テレワークの本格的な定着を支援する内容となっています。特に情報セキュリティ対策については、業務データの保護と柔軟な働き方の実現の両立が重要な課題となっており、従来の働き方改革をさらに推し進める新たなソリューションが求められています。
これらの課題に対して、データレスクライアントである「セキュアコンテナ」が新たな選択肢となっています。隔離されたセキュアな業務領域を生成し、その中でのみ業務を行うことができるため、端末内に業務データを残すことなく、高度なセキュリティを実現します。業務終了時にはその領域を削除するため、MDMの導入やリモートワイプを使用せずとも、万が一端末の紛失や盗難が発生した場合でも、重要なデータを失う心配がありません。さらに、スマートフォンやタブレットからのセキュアブラウザによる作業にも対応しているため、多様な働き方にも柔軟に対応できます。
CACHATTO Oneに関する資料請求やお問い合わせはこちら。
お気軽にお問い合わせください!
リモートアクセスや製品に関する
お役立ち資料をご用意しています。
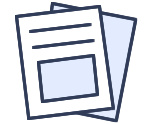 お役立ち資料ダウンロード
お役立ち資料ダウンロード
リモートアクセスや製品に関する
様々なご質問にお答えします。
 メールでお問い合わせ
メールでお問い合わせ