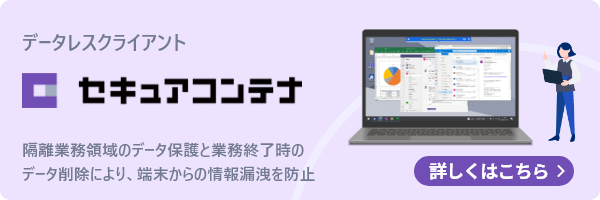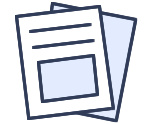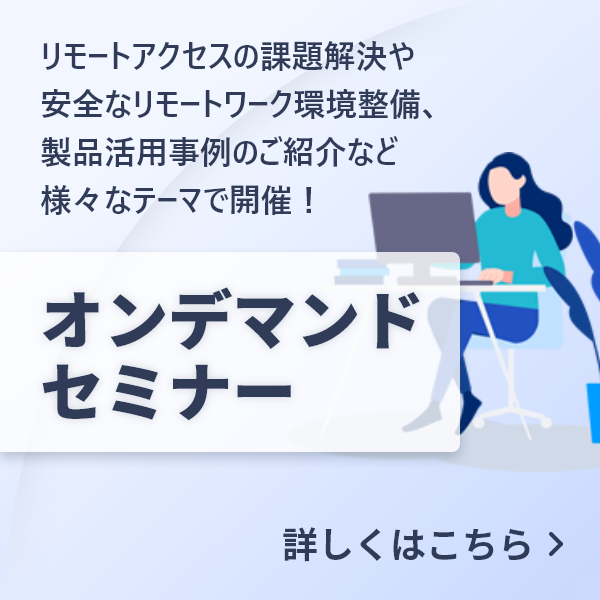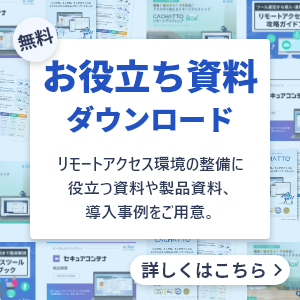製造業のテレワーク戦略と実現へのアプローチ
2025.07.01投稿、2025.07.01更新
製造業におけるテレワーク導入には、現場作業の存在や設備の遠隔管理、技術情報の取り扱いなど、製造業特有の課題が立ちはだかります。しかし、部門ごとの特性を理解し、段階的なアプローチを取ることで、確実な導入を実現できます。
本記事では、製造業におけるテレワーク可能な業務領域を明確にしたうえで、段階的な導入アプローチと適切なセキュリティ対策についてご紹介します。
製造業のテレワーク化における現状と課題
製造現場特有の制約や課題を理解しつつ、コロナ禍を契機に見えてきた可能性と限界を整理し、業務継続性の観点からテレワーク導入の重要性を解説します。
製造業特有の制約とは
製造業におけるテレワーク導入の最大の課題は、実際の製造現場での作業が必要不可欠という点にあります。製造ラインでの生産活動、設備の保守・メンテナンス、品質検査など、物理的な作業を伴う業務は、その性質上テレワークへの移行が困難です。これらの作業は、人の手による直接的な操作や目視確認が不可欠であり、現場での対応が必要となります。
また、製造業では製品の設計図面や製造プロセスなど、機密性の高い情報を扱うことも多く、情報セキュリティの確保も重要な課題となっています。さらに、生産計画の急な変更や品質トラブルへの対応といった場面では、現場の状況をリアルタイムで把握し、迅速な意思決定が必要となるため、物理的な距離が障壁となる可能性があります。
コロナ禍で見えてきた可能性と限界
製造業では従来、生産現場を中心とした業務特性から、テレワークの導入には慎重な姿勢が見られました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大により、業務の継続性を確保するためテレワーク導入の検討を余儀なくされ、実際に多くの企業がテレワークを試行したことで、これまで見えていなかった新たな可能性が明らかになってきました。
具体的には、管理部門や営業部門、製品開発・設計部門などで、デジタルツールの活用によって多くの業務をリモートで遂行できることが分かりました。設計レビューのオンライン化や、3DCADを活用した遠隔での設計作業、Web会議システムを利用した商談など、これまで対面を前提としていた業務のデジタル化が進展しています。
一方で、新製品の立ち上げ時における試作品の評価や製造ラインの改善活動、技術指導など、現場での直接的なやり取りが重要な場面では、完全なテレワーク化は困難であることも分かりました。これらの経験から見えてきたのは、定型的な業務や情報処理を中心とする業務はテレワーク化が可能である反面、製造現場特有の経験やノウハウの共有、現場での問題解決など、対面での直接的なコミュニケーションが必要な業務については、従来通りの働き方が不可欠だということです。
業務継続性の観点からみたテレワーク導入の重要性
大規模な自然災害やパンデミックなどの緊急事態において、事業を継続していくためには、テレワーク体制の整備が不可欠です。特に、設計・開発や生産管理など、製造現場以外の業務については、テレワークを通じた業務継続が可能であり、これを実現することで企業の事業継続性は大きく向上します。
また、テレワークの導入は危機管理対策としてだけでなく、働き方改革の推進にも大きく貢献します。育児や介護との両立が必要な従業員の就業継続支援や、地方在住の優秀な人材の採用など、人材活用の幅を広げることができます。さらに、通勤時間の削減による従業員の生産性向上や、オフィスコストの削減なども期待でき、企業の競争力強化にもつながります。
部門別テレワーク導入アプローチ
管理部門から製造現場まで、各部門の特性に応じたテレワーク導入の具体的な方法と、活用可能なデジタルツールについて詳しく解説していきます。
管理部門(経理・人事・総務)のテレワーク化
管理部門は、比較的テレワークへの移行が容易な部門とされています。経理業務では、クラウド会計ソフトの導入や電子帳簿保存法への対応により、請求書処理や経費精算、財務報告書の作成など、多くの作業をリモートで実施できます。
人事部門では、採用面接のオンライン化や人事評価のデジタル化、教育研修のオンライン実施など、従来の対面業務の多くをリモートに置き換えることが可能です。例えば、eラーニングシステムの活用により、社員教育や研修プログラムを効率的に実施できる利点があります。
総務部門においても、文書管理のデジタル化や社内コミュニケーションツールの活用により、多くの業務をテレワークに移行できます。電子承認システムの導入により、各種申請・承認業務もペーパーレスで効率的に処理することが可能になっています。
営業部門のテレワーク化
営業部門では、オンライン商談やWeb展示会に加え、製品のデジタルカタログ化やオンラインデモンストレーションを活用することで、対面営業を補完するリモート営業体制を構築し、移動時間を削減しながら効率的な営業活動が可能になります。
特に、既存顧客との定期的なフォローアップや基本的な商談については、オンラインでの対応が効果的です。CRMツールの活用による顧客情報の共有や商談履歴の管理により、チーム全体での営業活動の最適化も図れます。さらに、営業資料のクラウド共有により、最新の製品情報やプレゼン資料にいつでもアクセスできる環境を整備することで、より質の高い営業活動が実現できます。
製品開発・設計部門のテレワーク化
3DCADソフトウェアやシミュレーションツールの発達により、製品開発・設計業務の多くをリモートで実施することが可能です。クラウドベースの設計環境を整備することで、チーム間での図面や設計データの共有・確認作業もスムーズに行えます。また、VRやARなどの先端技術を活用することで、試作品の確認や設計レビューもリモートで実施できるようになりました。
なかでも設計変更や修正作業は、クラウド上で複数のメンバーが同時に作業することで、より効率的な開発プロセスを実現できます。さらに、3Dプリンタなどのデジタルツールを活用することで、試作品の製作と評価のサイクルも短縮化が可能です。
製造企画・生産管理部門のテレワーク化
生産計画の立案や在庫管理、サプライチェーンの管理など、多くの業務をデジタルツールを活用してリモートで実施できます。製造実行システム(MES)やERPシステムとの連携により、生産状況のリアルタイムモニタリングや生産計画の調整も可能です。
IoTセンサーやカメラを活用することで、製造設備の稼働状況や生産ラインの状態を遠隔で把握でき、生産進捗の確認や計画の見直しなども、現場に行かずに実施することが可能になっています。また、取引先とのコミュニケーションもオンラインツールを活用することで、スムーズな情報共有と意思決定が実現できます。
品質管理部門のテレワーク化
品質管理業務においても、IoTやAIを活用した遠隔監視システムの導入により、製品品質の監視や異常検知をリモートで実施できます。品質データの収集・分析や品質報告書の作成など、データに基づく業務については、テレワークでの遂行が可能です。
画像解析技術やセンサー技術の活用により、製品の外観検査や寸法測定なども自動化が進んでおり、検査結果のリモートでの確認が可能になっています。また、品質会議や改善活動についても、オンラインツールを活用することで、関係者間での情報共有や課題解決の討議を効率的に行えます。ただし、重大な品質問題が発生した場合など、現場での直接確認が必要な場面では、適切に現場対応との使い分けを行う必要があります。
テレワーク導入における情報セキュリティの確保
製造業特有の機密情報を安全に扱うためのセキュリティ対策と、データレスクライアントによる新たなソリューションを紹介します。
製造業特有の機密情報とその保護
製造業では、製品の設計図面や製造プロセス、原価情報など、競争力の源泉となる機密情報を多く扱います。テレワーク環境下でこれらの情報を安全に扱うためには、適切なセキュリティ対策が不可欠です。
とりわけ重要なのは、設計データや製造ノウハウなどの知的財産の保護です。クラウドストレージやファイル共有システムを利用する際は、暗号化通信の利用、アクセス権限の適切な設定、データの改ざん防止対策などを徹底する必要があります。また、取引先との機密保持契約に基づく情報管理も、テレワーク環境下で確実に実施できる体制を整える必要があります。
テレワーク時のセキュリティリスクと対策
テレワークにおける主なセキュリティリスクには、通信経路の盗聴、端末の紛失・盗難、マルウェア感染などがあります。これらのリスクに対しては、VPNの利用による通信の暗号化、多要素認証の導入、エンドポイントセキュリティの強化などの技術的対策が必要です。
また、従業員に対するセキュリティ教育も欠かせません。テレワーク時の情報取り扱いルールの徹底や、不審なメールへの対応方法、安全なパスワード管理など、基本的なセキュリティ意識の向上が求められます。さらに、定期的なセキュリティ監査やインシデント対応訓練を実施することで、リスクの早期発見と対応力の向上を図ることができます。
データレスクライアントが解決する課題
テレワーク時の情報セキュリティ確保の有効な解決策として、データレスクライアントの活用があります。これにより、端末内に業務データを残すことなく、安全な業務環境を実現できます。また、業務用の領域を隔離することで、私用端末でのテレワークにおいても業務データの漏洩リスクを最小限に抑えることができます。
クラウドベースのシステムとの連携により、常に最新のセキュリティ対策が適用された環境で業務を行うことができ、端末紛失時のリスクも大幅に低減できます。また、アクセスログの管理や操作履歴の記録により、セキュリティ監査の実効性も高めることができます。
さらに、データレスクライアントの主要な特徴として、ネットワーク環境のない場所でも一部のオフライン作業が可能という点が挙げられます。出張先や移動中はもちろん、製造現場でも必要な業務を継続できることは、製造業における柔軟な働き方を実現する上で大きなメリットとなります。
データレスクライアントについては、次の記事も参考にしてください。
関連記事

データレスクライアントとは?仕組みやVDIとの違い、メリット・デメリットを解説
段階的導入のためのロードマップ
試験導入から全社展開まで、各フェーズにおける具体的な実施事項と注意点を整理し、着実な導入を実現するためのステップを解説します。
フェーズ1:試験導入と課題抽出
テレワーク導入の第一段階として、特定の部門や業務を選定して試験導入を行います。製造業の場合、比較的テレワークへの移行がスムーズな管理部門(経理・人事・総務)や、デジタルツールの活用が進んでいる製品開発・設計部門からスタートすることをお勧めします。これらの部門は既存のITインフラを活用できるうえ、業務の大部分がデータ処理や情報共有で完結するため、初期段階での成功確率が高くなります。
この段階では、必要な機器やツールの選定、運用ルールの策定、セキュリティ対策の検証などを実施します。優先すべきは、テレワーク環境での業務効率や品質の維持が可能かどうかの検証です。試験導入を通じて発生する課題や改善点を洗い出し、本格導入に向けた準備を進めます。従業員からのフィードバックを積極的に収集し、使いやすい環境作りと運用ルールの最適化を図ります。最初の試験導入で成功事例を作ることが、その後の全社展開をスムーズに進める上でのカギとなります。
フェーズ2:本格展開と定着化
試験導入で得られた知見をもとに、テレワーク対象部門を拡大し、本格的な展開を進めます。この段階では、業務プロセスの見直しやマニュアルの整備、評価制度の調整なども併せて実施します。特に、テレワーク環境下での適切な労務管理や評価方法の確立が重要です。
また、従業員のテレワークスキル向上のための研修や、マネージャー向けのリモートマネジメント研修なども実施します。コミュニケーションツールの効果的な活用方法や、テレワーク時の健康管理についても、具体的なガイドラインを整備します。
フェーズ3:全社展開と最適化
最終段階では、テレワーク可能な全部門への展開を図り、より効率的な業務運営を目指します。定期的な効果測定や従業員アンケートを実施し、継続的な改善を図ります。特に、業務効率や従業員満足度、コスト面での効果を定量的に測定し、運用方法の最適化に活かします。
また、デジタルツールの活用度を高め、より生産性の高い働き方の実現を目指します。部門間の連携強化や新たなビジネスプロセスの確立など、テレワークを活用した業務改革も積極的に推進します。
安全で効率的なリモートワークの実現に向けて
製造業におけるテレワーク導入は、製造現場での作業が必要不可欠という特性から、一見すると困難に思えるかもしれません。しかし、部門別の特性を理解し、適切なアプローチを取ることで、着実な導入が可能です。管理部門や製品開発・設計部門など、比較的テレワークへの移行がスムーズな部門から段階的に開始し、実績と経験を積み重ねていくことが成功への近道となります。
一方で、製品の設計図面や製造プロセスなど、機密性の高い情報を扱う製造業ではセキュリティ対策が不可欠です。この課題に対して、データレスクライアントの活用が有効な解決策となります。例えば、データレスクライアントである「セキュアコンテナ」は、端末内にセキュアな業務領域を作り出し、業務終了時にはその領域を削除することで、データ漏洩のリスクを大幅に低減します。さらに、スマートフォンやタブレットにも対応しているため、より柔軟な働き方を実現できます。
このように、適切なツールと段階的なアプローチを組み合わせることで、テレワークは一時的な対応策ではなく、製造業の競争力を高めるための重要な経営戦略として機能していくでしょう。
CACHATTO Oneに関する資料請求やお問い合わせはこちら。
お気軽にお問い合わせください!
リモートアクセスや製品に関する
お役立ち資料をご用意しています。
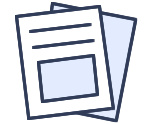 お役立ち資料ダウンロード
お役立ち資料ダウンロード
リモートアクセスや製品に関する
様々なご質問にお答えします。
 メールでお問い合わせ
メールでお問い合わせ