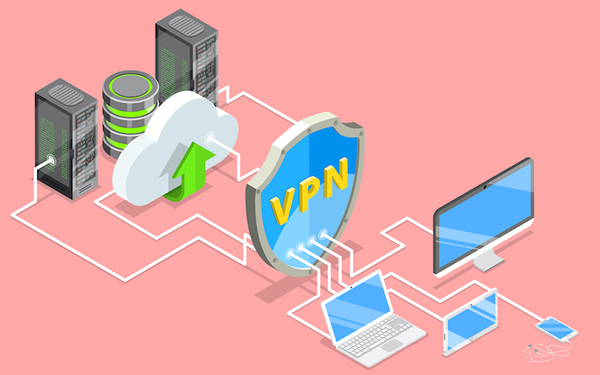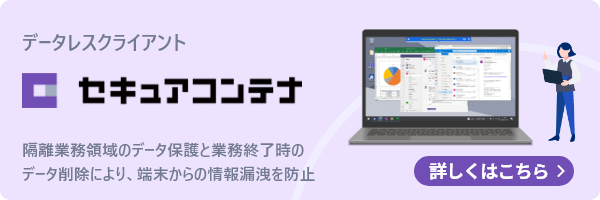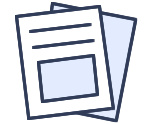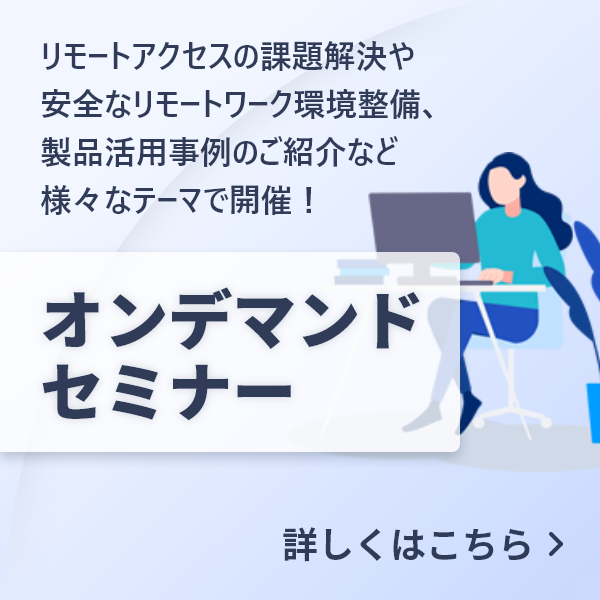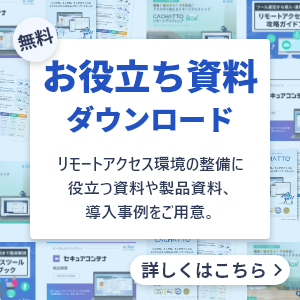今、問われるVPNを活用した社内ネットワーク
2025.05.08投稿、2025.05.08更新
企業のデジタル化が加速し、多様な働き方へのニーズが高まる中、社内ネットワークのあり方は大きく変わろうとしています。多くの企業がVPNを活用して社外からの安全なアクセスを確保していますが、実際の運用では通信速度の低下、セキュリティ上の懸念、運用管理の煩雑さといった課題に直面しています。
本記事では、社内ネットワークにおけるVPNの基本的な仕組みから運用課題、その改善策まで、現場のIT担当者の視点で解説します。さらに、ゼロトラストモデルなど新しいセキュリティアプローチの可能性についても探ります。
VPNによる社内ネットワーク構築の基礎知識
社内ネットワークのセキュリティ確保に広く活用されているVPNについて、その基本的な仕組みと主な方式、そして現在の役割を解説します。
VPNの仕組みと主要な方式の比較
VPN(Virtual Private Network)は、インターネットなどの公衆回線上に、暗号化された安全な通信経路を作り出す技術です。この仮想的なトンネルを通じて、離れた場所にある拠点同士があたかも同じネットワーク内にあるかのように接続することができます。
具体的には、データを送信する際に暗号化を行い、受信側で復号化することで、通信経路上での情報の盗聴や改ざんを防ぎます。例えば、社外から社内システムにアクセスする場合、VPNを使用することで、インターネットカフェのような公共のWi-Fiスポットからでも、安全に社内の機密情報にアクセスすることが可能になります。
VPNの主要な方式には、大きく分けてIPsecとSSL/TLSの2種類があります。IPsecは通信機器レベルでネットワーク全体を暗号化し、高いセキュリティを確保できる反面、専用機器の設置や複雑な初期設定が必要になります。一方、SSL/TLSは、一般的なWebブラウザを使用して特定のアプリケーションだけを暗号化する方式です。導入が容易で柔軟な運用が可能ですが、アプリケーション単位での設定が必要になります。
VPNについては、次の記事も参考にしてください。
関連記事
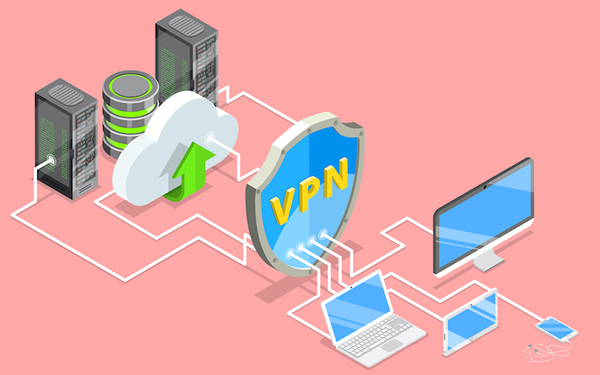
VPNとは?仕組みやプロトコルの種類、接続方式などを解説
社内ネットワークにおけるVPNの役割
社内ネットワークにおいて、VPNは単なる通信経路以上の役割を果たしています。社外からのセキュアなアクセス手段としてだけでなく、複数拠点間の接続、クラウドサービスとの連携など、現代のビジネスに不可欠な機能を担っています。特に、リモートワークが一般化する中で、その重要性はますます高まっています。
VPNを活用した社内ネットワークの導入メリット
専用線と比較したコスト面での優位性や、リモートワーク環境の実現など、多くの企業がVPNを選択する理由を解説します。
セキュリティ強化とコスト削減の両立
企業がVPNを導入する最大のメリットは、高度なセキュリティを確保しながら、インフラコストを大幅に削減できる点にあります。従来の専用線では、拠点間を物理的な専用回線で接続する必要があり、その敷設費用や月額利用料は企業にとって大きな負担となっていました。一方、VPNでは、強固な暗号化技術により専用線と同等のセキュリティレベルを保ちながら、インターネット回線を利用することで通信コストを抑えることができます。特に、複数の拠点をつなぐ必要がある企業や、社外からの安全なアクセスを必要とする企業にとって、このコストパフォーマンスの高さは大きなメリットです。
リモートワーク環境の整備と生産性向上
多様な働き方が広がる中、VPNは社外での業務を支える重要なインフラとなっています。社員は自宅や出張先からVPNを通じて社内システムにアクセスすることで、オフィスにいるときと同じように業務を進めることができます。セキュリティを確保しながら社内の各種システムやデータにアクセスできることは、場所を問わない働き方を実現する上で不可欠な要素です。
営業担当者であれば、外出先から社内の顧客データベースに安全にアクセスして商談の準備を整えたり、在宅勤務者は自宅から社内の共有フォルダにある資料を参照しながら資料作成を進めたりすることができます。このように、業務に必要な情報やツールへのアクセスが制限されないことで、働く場所や時間を柔軟に選択できるようになり、従業員の生産性向上にもつながっています。
VPNを活用した社内ネットワークの課題
VPNは、セキュリティ強化やインフラコスト削減といった大きなメリットがある一方で、課題も浮き彫りになってきています。ここでは、VPN環境で企業が直面している具体的な課題について説明します。
帯域幅とパフォーマンスの問題
VPNの運用における最大の課題は、帯域幅とパフォーマンスの問題です。通信データの暗号化と復号化が常に行われるVPNでは、通常のインターネット接続と比較して通信速度が低下しがちです。この処理にはCPUリソースも必要となるため、端末の性能によって動作が大きく影響を受けます。
加えて、多くのユーザーが同時にVPN接続を利用する場合、共有帯域が逼迫し、通信速度がさらに遅くなる傾向があります。在宅勤務が増加した環境では、大容量ファイルの転送やリアルタイムのビデオ会議など、帯域を大量に使用するケースが頻発します。その結果、画面表示の遅延や音声の途切れ、ファイル保存に要する時間の増加といった問題が発生し、業務効率が損なわれる原因となります。
VPN特有の脆弱性と対策の必要性
VPNは社内ネットワークのセキュリティを確保する技術ですが、その一方で、VPN特有の仕組みに起因するセキュリティリスクも存在します。特に、近年はVPNクライアントの脆弱性を悪用した攻撃が増加しており、古いバージョンのクライアントソフトウェアが狙われやすい状況です。また、ブルートフォース攻撃による認証情報の漏洩や、フィッシング詐欺を通じたVPN認証情報の窃取といった、認証を突破しようとする手口も後を絶ちません。
これらのリスクに対応するためには、VPNクライアントの定期的なアップデート、多要素認証の導入、アクセスログの監視など、複数の対策を組み合わせる必要があります。さらに、不正アクセスを検知した際の対応手順の整備や、従業員へのセキュリティ教育も欠かせません。これらの対策は、セキュリティレベルを維持する上で必須ですが、組織にとって大きな負担となっています。
運用管理の負担と人的コスト
運用管理の負担も無視できない課題です。IT部門は、ユーザーアカウントの作成・変更・削除の管理や、VPNクライアントソフトウェアの配布・更新作業を継続的に行う必要があります。また、リモートワーカーからの接続トラブルの問い合わせ対応や、ネットワークの障害切り分けなど、日常的なサポート業務も発生します。
さらに、セキュリティポリシーに基づくアクセス権限の設定や、部署ごとのアクセス制御ルールの管理など、詳細な運用管理も求められます。これらの作業を適切に行うためには、専門知識を持った人材の確保や、運用チームの体制維持が必要となり、結果として人的コストの増加につながっています。また、担当者の育成や、ナレッジの継承といった長期的な課題も存在します。
VPN環境の最適化とパフォーマンス改善策
これらのVPNを活用した社内ネットワークにおける課題に対して、既存のVPN環境を改善するための対策と、ゼロトラストモデルなど新しいセキュリティアプローチの可能性について説明します。
通信速度とユーザー体験の改善
VPNの通信速度を向上させるには、トラフィック制御を最適化することが最も効果的です。業務に必要な通信を優先的に処理するQoS(Quality of Service)を設定すれば、重要な業務データのやり取りをスムーズに行えます。例えば、ビデオ会議システムの通信を優先することで音声の途切れやフリーズを防ぎ、大容量ファイルの転送など即時性が求められない通信は優先度を下げることで、全体の通信効率が向上します。
さらに、キャッシング機能を活用することで、頻繁にアクセスされるデータをローカルに保存し、VPN経由の通信量を減らすことが可能です。また、VPNサーバーの適切な配置や負荷分散の実装により、地理的な遅延を最小限に抑えられます。これらの対策を組み合わせることで、ユーザーの体感速度を大幅に改善できます。
セキュリティと運用管理の効率化
統合管理ツールの導入によって、VPN環境の運用課題を大幅に改善することが可能です。これらのツールを活用すれば、ユーザー管理やアクセス権限の設定、セキュリティポリシーの適用を一元的に実施できます。例えば、新入社員のアカウント設定や部署異動時の権限変更を自動化し、退職者のアクセス権限を迅速に無効化するといった効率化が期待できます。
また、セキュリティアップデートの自動配信機能を用いることで、すべてのVPNクライアントを最新の状態に維持できます。さらに、リアルタイム監視機能により、不審なアクセスパターンや異常な通信を即座に検知し、セキュリティインシデントを早期に発見して対処することが可能です。これらの自動化や可視化の取り組みは、IT部門の運用負荷を大幅に軽減するだけでなく、より高度なセキュリティ管理を実現します。
新たな選択肢:ゼロトラストとデータレス化への展開
より根本的な解決策として注目を集めているのが、ゼロトラストモデルへの移行です。従来のVPNは、社内ネットワークと外部を明確に区別する「境界型セキュリティ」を前提としていました。しかし、クラウドサービスの普及やリモートワークの一般化により、このような境界を前提としたセキュリティモデルには限界が見えてきています。
ゼロトラストモデルでは、「信頼できるネットワークは存在しない」という考え方のもと、すべてのアクセスを継続的に検証します。ユーザーの認証情報だけでなく、アクセス元の端末の状態、アクセス時の場所や時間帯、要求される操作の内容など、複数の要素を総合的に評価して認証を行います。この方式により、きめ細かいアクセス制御が可能となり、セキュリティリスクを最小限に抑えながら、ユーザーの利便性を確保できます。
さらに、ゼロトラストの考え方を発展させた解決策として、データレスクライアントという選択肢が登場しています。この方式では、端末内にセキュアな業務領域を作り、業務終了時にはその領域を完全に削除することで、データ漏洩のリスクを大幅に低減します。また、これらの新しいアプローチは、従来のVPNで課題となっていた運用管理の負担も軽減するため、IT部門の負荷削減や業務効率化にもつながります。
このように、VPN環境が抱えるさまざまな課題に対して、新技術を活用した解決策の選択肢が広がりつつあります。
ゼロトラスト、データレスクライアントについては、次の記事も参考にしてください。
関連記事

ゼロトラストとは?メリットやデメリット、実現するためのポイントを紹介
関連記事

データレスクライアントとは?仕組みやVDIとの違い、メリット・デメリットを解説
これからの社内ネットワークを考える
VPNは、セキュリティと効率性の両立、リモートワーク環境の整備など、多くのメリットをもたらしてきました。しかし、実際の運用では、帯域幅とパフォーマンスの問題、VPN特有の脆弱性、運用管理の負担など、様々な課題が浮き彫りになってきています。多数のユーザーが同時にアクセスする環境では、これらの課題がビジネスの効率性に大きな影響を与えています。
これらの課題を根本的に解決するには、従来のVPNに依存しない、より柔軟で安全なアクセス方式への移行が必要です。
その解決策として注目を集めているのが、データレスという新しい考え方です。例えば、データレスクライアントである「セキュアコンテナ」は、端末内にセキュアな業務領域を作り出し、業務終了時にはその領域を完全に削除することで、データ漏洩のリスクを大幅に低減します。従来のVPNが抱えていた運用管理の負担も軽減され、スマートフォンやタブレットにも対応することで、より柔軟な働き方を実現できます。
CACHATTO Oneに関する資料請求やお問い合わせはこちら。
お気軽にお問い合わせください!
リモートアクセスや製品に関する
お役立ち資料をご用意しています。
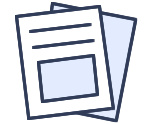 お役立ち資料ダウンロード
お役立ち資料ダウンロード
リモートアクセスや製品に関する
様々なご質問にお答えします。
 メールでお問い合わせ
メールでお問い合わせ